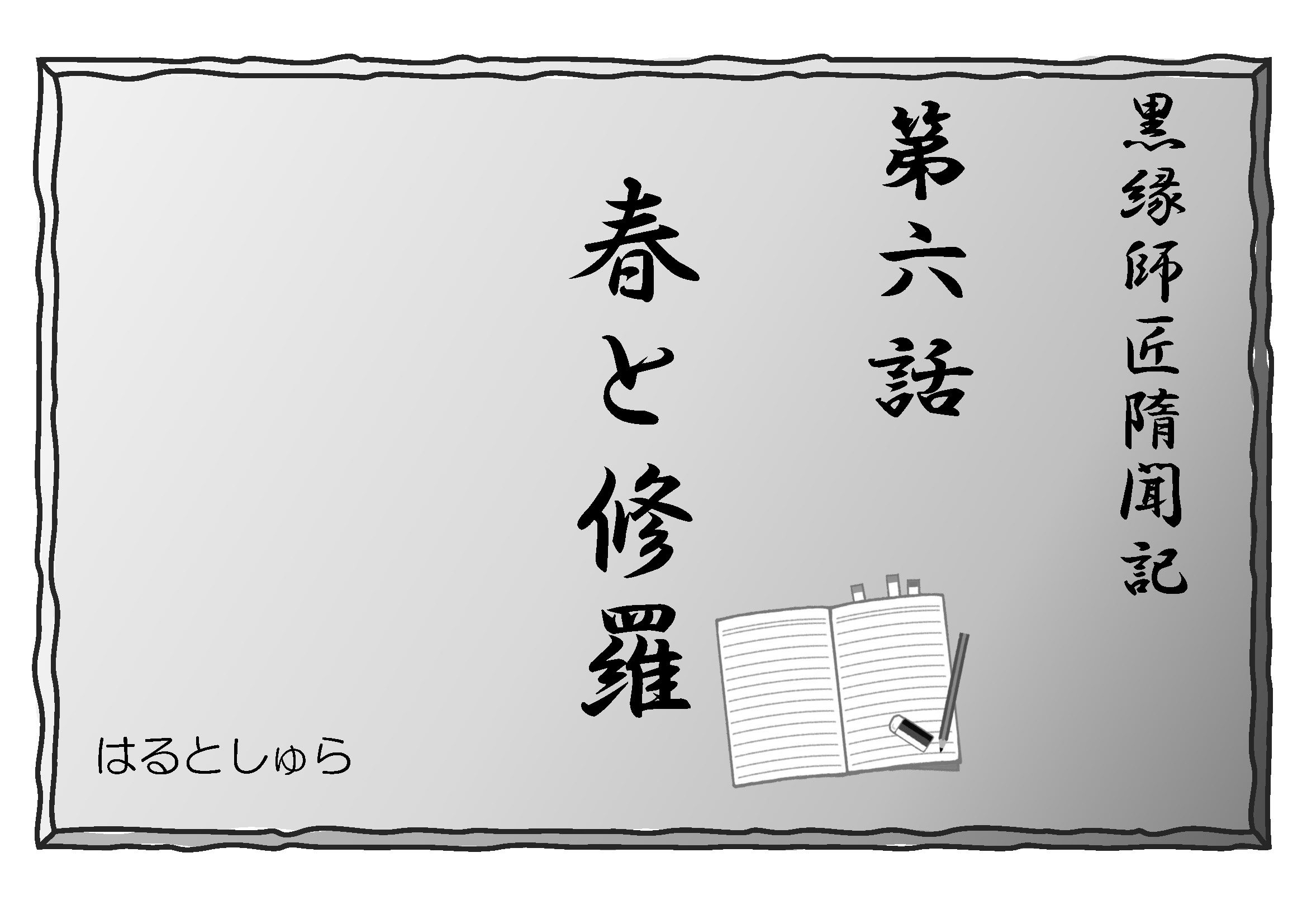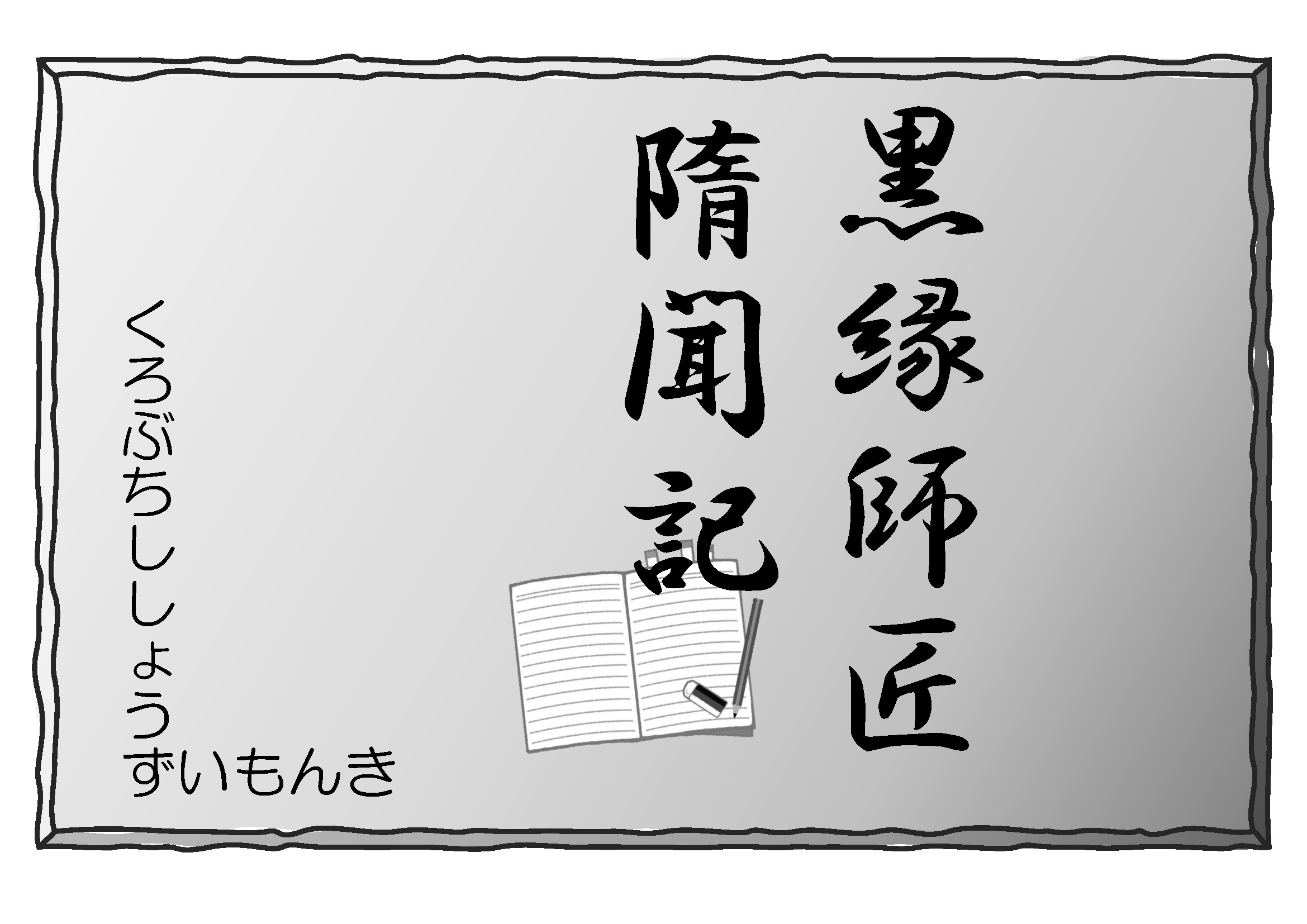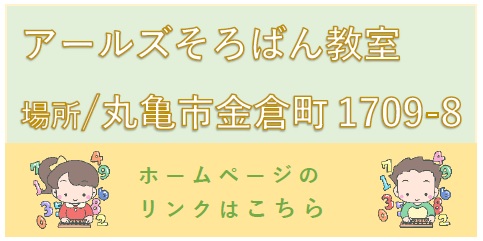7月に入り、颯一郎の心は乱れていた。
期末テストの成績が返ってきたものの、結果は思わしくない。
「行く高校がない」
5月の懇談会で担任にそう言われた颯一郎は、奮起した。
「どうせ覚えられないから」とあきらめの気持ちはなるべく振り払うようにした。
いつか、黒縁先生にそのことを注意されていたからだ、特に社会は問題集を何度も解いた。
「『どうせ』とか『めんどくさい』という気持ちを心に残したまま勉強するんじゃねえぞ」
黒縁先生がいつも言っていた。
自分はこれまで、この黒縁先生の言葉を分かっていたつもりになっていただけだった。
しかし、今回のテスト勉強で、なんとなく腑に落ちたかもしれない。
「テスト勉強って、こんな感じでやればいいんだ」
そういう手応えのようなものが颯一郎にはあった。
しかし、実際のテストの結果は、あまりいつもと変わらない。
颯一郎は少なくない衝撃を受けていた。
そして、自分なんかが、本当に成績を上げることができるのだろうかという不安、
「やっぱり自分なんてこんなもんだ」という気持ちが、颯一郎の心を支配しつつある。
その一方で、部活は総体が迫っており、練習には熱が入る。
練習に熱が入ると、その分、家や塾ではなんだか疲れて勉強する気が起きない。
しかし、このままの成績では、「行く高校がない」と言われたままの結果となってしまう。
まさに、部活と塾の板ばさみで思い通りにならない歯がゆさを颯一郎は感じていた。
昨日先生に渡された期末テストの結果を、お母さんには見せたくなかったけれども、見せないわけにもいかない。
どうせ次の懇談会で、この成績を見られることになるからだ。これも颯一郎のストレスになった。
無論、これらの問題点について、明晰に整理して内省する力は、今の颯一郎にはまだない。
颯一郎は、お腹のみぞおち辺りに広がる原因不明の「もやもや」としてこれらのストレスを感じ、そして持て余すだけであった。
その「もやもや」は、鉛のように重く感じることもあれば、煙のようにつかみどころがないこともあった。
とても颯一郎の手に負えるものではない。
ある時、颯一郎は夢想した。
自分の腹に広がる「もやもや」を両手でかき集め、泥団子のようにぎゅっと丸めて、どこかに放り投げたらきっと気が晴れるだろうな、などと想像してみた。
しかし、泥団子を放り投げたあと、どうせまたすぐに新たな「もやもや」がどす黒い煙のようにやってくるに違いないと思い直し、颯一郎は思わず大きなため息をついた。
この日、ついに颯一郎は筆箱の中に折りたたんでしまっておいた、期末テストの結果が印字された紙をお母さんに見せることにした。
紙は横に細長く、9教科それぞれの得点と学年順位、そして、5教科合計、9教科合計の得点と学年順位が印刷されている。
5教科合計は、学年120名中101位。9教科合計も似たようなものだった。
たしかに、前回の学年順位からは、5位ほど上がっているものの、今回の颯一郎の目標は100位以内だった。
颯一郎が、
「お母さん、これ・・・・・・」
と台所にいたお母さんに紙を手渡す。
颯一郎は、お母さんの顔を直視することができずにいた。
紙を渡されたお母さんは、何か言いたいのをこらえるように、しばらくじっと黙っていたが、やがて口を開く
「まあ、少し上がったみたいね。颯クン頑張ってたもんね。でも、やっぱり……塾変えた方がい・・・・・・」
お母さんがそう言いかけた時、颯一郎は強く反応した
「うるせえ! 黙って見てろ! 合格すりゃいいんだろ、合格すりゃ!」
颯一郎の権幕に驚くように、お母さんはリビングの椅子にへなっと座りこんでしまった。
反抗期らしい反抗期もなかった颯一郎が、こんな風に、親に乱暴な口をきいたのは、たぶん初めてだった。
「あ・・・・・・ごめん、お母さん・・・・・・」
母親に向かって乱暴な言葉を浴びせたことに、一番驚いていたのは颯一郎自身かもしれなかった。
(ちがう、自分は親にこんな口をきくような人間じゃない・・・・・・)
頭が真っ白になって、もう何をどうすればいいか分からない。
呆然と立ちつくす颯一郎に、先ほどは驚いていたものの、気を取り直したお母さんが声をかけた。
「えっと・・・・・・ねえ。そうね、『勉強のことは、本人にまかせて、何も言わないのが一番だと思う』って、お父さんも言ってたから。でも、本当に今の塾のまま本番まで行っていいの?」
颯一郎は、こくこくと何度かうなずくだけだった。
おれは、変わったんだ。
おれは、今までになく勉強したんだ。
もうすぐ何かがつかめそうなんだ。
その『つかめそうな何か』は、あの教室でなければ、あの教室意外ではこの手からこぼれ落ちそうな気がする。
理屈ではない。
颯一郎は、そう信じていたものの、それをうまく説明することは、今は絶対に無理だと思う。
何を言っても、起こっていない未来に対して、しかし、「絶対そうなる」と颯一郎本人だけが確信している何かを、
颯一郎以外の人間に説明することは不可能に決まっている。
「根拠は?」と聞かれたら、「そうなると信じているから」としか答えられない。
しかし、それを言ったところで、説得力がないことは颯一郎にも分かっている。
何を言ったって、どうせ信じてもらえない。
下を向いて、しかし、石のように何かを心に決めているような表情の颯一郎を見て、お母さんは
「わかったわ・・・・・・」
と言った。
その声には、あきらめと不安が混在しているようだった。
颯一郎は、塾用のリュックを背負って下を向いたまま出かけて行く。
リビングから出ていく颯一郎の背中に
「いってらっしゃい」
小さな声でお母さんが声をかけた。
その日の颯一郎が沈んだ顔で教室に入ってきたのを、黒縁は見逃していなかった。
だが、黒縁は颯一郎には触れることもなく、まだ教室に残っている数人の小学生相手と、わいわいやっている。
いつもならば、そんな小学生と黒縁のやりとりを、楽しみながら見たり、時には自分も参加したりする颯一郎だったが、この日は遠くの花火を眺めるようにぼんやり見ていた。
小学生が帰って、教室にいる生徒が颯一郎だけになったタイミングで、黒縁が颯一郎に声をかける。
「ご機嫌斜めだな」
たしかに、今日の颯一郎は、いつもよりは幾分むくれた顔をしているのだろう。
それは颯一郎自身も自覚していた。
だからと言って、どうすることもできない。
気分が悪いものは悪いのだ。
しかし、颯一郎はあえて声のトーンを上げて黒縁にぶつけることにした。
「師匠! がんばったのに、成績上がりません! オレ、がんばったんですよ!」
颯一郎のそんな風圧を、しかし黒縁は春風にそよぐ柳のごとく受け流す。
そして、あごに手をやり、剃り残したひげをつまみながら言った。
「ええか、颯一郎。まず、その考え方がそもそも違う」
「え?」
「あのなあ……まあ、たとえば『Aという結果』を得たいとするよな。そのとき、人は『Aという結果』を得るために行動する。その行動を『がんばった』とか『努力した』と、まあいろいろ表現するわけやけど、そんなんはどうでもええんや」
「え、だって、結果って大事ですよね。がんばったのに、成績上がらなかったら、勉強する意味ないじゃないですか」
颯一郎が不満そうにこぼす。
「結果、結果、うるさいねん、お前らは。『がんばったけど、結果が出なかった。だから、おれはダメなやつや』という考えが一番あかん」
「まさに、今のオレです・・・・・・」
「そやな。それは考え方の矢印がまるで逆になってて。『がんばったけどダメだった』という考えは捨てて、『できるまでやる』という考えでやるのが本当にできる奴の心の構えやねん。それに、どうせまだ『おれは覚えが悪いし』とか思いながら勉強やってるやろ」
「でも、おれ実際、記憶力悪いし・・・・・・」
「だから、それが『言い訳や』と言うてるんや。たしかに、世の中には記憶力の悪い人間もおる。お前は心配せんでも、ふつうに『言い訳派』やから、今後は一切言い訳するな。あと、この教室で腐った面しよったら叩き出すぞ」
「はい・・・・・・」
「成績上げたろと思って、これまで以上にテスト勉強したんやろ?」
「そうなんです」
「でも、勉強したのに成績はそれほどでもなかったんやろ?また、100位前後でうろちょろしてるんやろ、どうせ」
「師匠・・・・・・なんで分かるんですか?」
「ああ、プロだから」
言いながら、黒縁はメガネをクイッと持ち上げ、続ける。
「『できるまで、やる』っていう覚悟、あるか?」
メガネの奥から見つめる黒縁の視線が、真っ直ぐに颯一郎に突き刺さる。
一点の曇りもない、何にも動じない、妥協も許さない。
そういう視線であると、颯一郎も直感的に悟っていたのかもしれない。
「もっと、教えてほしいです。お願いします」
この時、颯一郎は、素直な気持ちで頭を下げていた。
「じゃあ、次から30分居残りな。英語の教科書持ってこい」
「え、それだけでいいんですか?」
「十分や」
その次の日から、颯一郎の英語の特訓が始まった。
特訓と言っても、特別なことではない。
英語の教科書を、ひたすら音読するというだけのことだった。
それを30分居残りでやる。
颯一郎が教科書を読んでいる間、目の前に座った黒縁先生は何をしているかと言えば、ずっとスマホを見ている。
それなのに、颯一郎が、教科書の本文を読み間違えたり、発音が少しおかしかったりするとすぐに
「違う」
と訂正された。
そればかりか、どう発音するのか分からなくて止まると
「arrive at」
などと言って読み方を教えてくれる。
「黒縁先生は教科書を見ていないのに」だ。
不思議になった颯一郎が、
「師匠、もしかして教科書を覚えているんですか?」
と聞くと、
「いや、覚えてない。けど、分かるやん」
「分かるやん、って……」
そこで黒縁は、突然
「『かぁ~めぇ~はぁ~めぇ~』って聞いたら、続きどう?」
「『はああああ!』です」
「それと一緒や」
「全然違うと思うんですけど……」
「ええから、続き読め。とりあえず、夏休み終わるまでは続けるぞ」
「はい・・・・・・」
英語と同時に、歴史の特訓も始まった。
「なぞってこい」
黒縁先生に渡された紙に、歴史の人物や事件などの用語が漢字で薄い色で書かれている。
A4サイズの紙が10枚ほどあり、そこにびっしりと歴史人物や事件の漢字で埋まっている。
颯一郎は漢字が苦手で、例えば「後鳥羽上皇」でも「ごとばじょうこう」と書いてしまうタイプであった。
これについて、以前から黒縁は、
「漢字率を上げると点数が上がるぞ。今のままの点数でええならひらがなで書け。まあ、好きにしたらええけど」
と何度か言ってきた。
「あ、なぞるだけじゃなくて、読めるようにしとけよ」
と黒縁が付け加えた。
「え、読みもですか? でも読み仮名ないので分かりません」
と颯一郎がちょっとした弱音を吐くと、
「ああああああ?」
黒縁が首をかしげてすごんできたので、颯一郎は
「あ、え、なんでもありません!」
と引き下がる。
「全部なぞって、読めるようにしとけ、ええな」
低い、どすの利いた黒縁の言葉に、颯一郎は
「はい・・・・・・」
と返事するしかなかった。
教室を閉めた後の階段を下りながら、颯一郎は黒縁に疑問をぶつけた。
「師匠。なんで今まで、今みたいな勉強法をおれに教えてくれなかったんですか?」
黒縁は、すぐに返事をすることなく、階段を下り、そして、階段を下りきったところで、一言発した。
「プロ、だから?」
「あ、はい……」
「ボスを倒したいと本気で思ってない奴に、便利な武器与えてもしょうがないと思ってる派やねん・・・・・・」
それだけ言って、黒縁は駐車場へすたすたと歩き去った。
颯一郎が帰宅し、リビングに入ると、お父さんとお母さんと綾子の3人がダイニングテーブルを囲んでおしゃべりをしている。
「颯兄ぃ、いよっ」
右手をひょいと上げて綾子は颯一郎に挨拶する。
綾子は今年小学5年生になるいとこだ。
小柄だけど、すらりとした手足は、すばしっこそうな印象を与える。
整った顔立ちに、さらさらのロングヘアーを後ろで一つに束ねており、
黙っていれば美少女とも言えなくもないかもしれないが、颯一郎はよく知っている。
綾子はとにかくよくしゃべる。
ずっとしゃべっている。
(ああ、またうるさいのが来た)
これが、颯一郎が一年ぶりに綾子を見て最初に思ったことだ。
「ということで、綾ちゃんは夏休み終わるまでうちで預かることになったからな、颯一郎」
ということって、どういうことだよと思ったりもしたが、これまでも綾子をうちで預かることは何度かあったので、颯一郎は特に驚きはしなかった。
颯一郎がテーブルにつくと、お母さんが颯一郎の前に夕食を並べながら言う。
「それでね、颯クン、夏休みの間だけど、綾ちゃんのお勉強を見てあげてほしいの。颯クンも自分の勉強で大変だと思うけど」
「え……」
颯一郎が戸惑っていると、
「いい復習になると思うぞ、颯兄ぃ、ひひひ」
と綾子がいたずらっぽく言う。
「でも、おれ、自分の勉強もあるし・・・・・・そ、そうだ。綾子もおれと一緒に黒縁先生んとこ行くっていうのはどう?」
と、心にもないことを颯一郎が口走る。
そして、口走った直後に「あ、しまった・・・・・・」と颯一郎は思った。
綾子と一緒に黒縁先生のところに行くなんて、もしかしたら自分が一番嫌かもしれない。
「え、なになに? 黒縁先生って、何? 颯兄ぃが行ってる塾? 行きた~い。綾子も行きたぁ~い」
「はっはっは、それも面白いかもな」
無責任に笑うのは颯一郎のお父さんだ。
「せっかくだし、夏休み限定で、行ってこいよ」
なにが「せっかく」だよと颯一郎が思っていると、今度はお母さんが心配そうに言う。
「そんな、大丈夫かしら……綾ちゃんが一緒に行って、颯一郎の邪魔にならないかしら……」
もちろん、お母さんが、颯一郎の「邪魔になるかどうか」を本気で心配しているのではない。
お母さんは単に黒縁先生を信用しきれないでいるのだ。
お母さんの思いはこうだった。
「いい先生がいる」という噂を聞いて、颯一郎が中1の時から預けたものの、成績が上がる気配がこれまで全くなかった。
これは、毎月授業料を払いながら通わせている身としては、文句の一つや二つは言いたくなる。
たしかに、颯一郎に問題がなかったとは思わない。
つい最近までの颯一郎に、勉強する気が全くなかったのは確かだし、それは親としても認識している。
しかし、それにしても「何かやりようがあったのではないか」と思ってしまう。
これまで成績が全く上がらなかった颯一郎の成績を、「あの先生」が上げてくれるとは思えない。
本当に信じていいのかどうか、母親としてはまだ揺れているものの、夏休み前に颯一郎が見せたすごい剣幕のことも同時に思い出す。
「うるせえ! 黙ってみてろ!」
と言った時の颯一郎の目。
親に向かって言っていい言葉ではない。
しかし同時に、これまで母親の自分でも見たことのないような強い意志を颯一郎に感じた。
それは、颯一郎の自分に対する確信なのか、それとも颯一郎と黒縁先生のつながりと断ち切ろうとしたことへの反発なのか・・・・・・
「綾子、邪魔しないし! ねえ、おじさん、お願いお願い」
「うん、分かった。ということで、お母さん、黒縁先生にお願いしてみてよ。あの教室だし、どうせ月謝もそんなにかからないだろう」
お母さんの思いなど関係なく、事態が進行する。
綾子とお父さん、この2人を食い止める方法も、言葉も、このときのお母さんには浮かばなかった。
「そうだ、いいこと思いついた!」
お父さんが思いつく「いいこと」が「いいこと」だった試しがない。
「明日、おいらが綾子を連れてご挨拶に行ってくるよ。黒縁先生ってのがどんな人か、いっぺん会ってみたかったんだ」
ふうっとあきらめるように息を吐いて、お母さんは洗い物に取り掛かる。
こうなってしまうと、もう誰も止めることができない。
もう抵抗するのもバカバカしかった。
颯一郎は颯一郎で、自分の思ってもみない発言から、綾子と一緒に塾に行くことになってしまい、
「まずいことになった」と思っていた。
しかし、何がどう「まずい」のかは、言葉にできない。
自分のきっかけで、思いもよらない方向に現実が動く・・・・・・ことのき、何の脈絡もなく?
そう、何の脈絡もなく、
颯一郎の頭には、黒縁の教室で覚えさせられた詩の一節が浮かんだ。
「わたくしという現象は 仮定された有機交流電燈の ひとつの青い照明です・・・・・・」
思わず口に出てしまった。
黒縁の教室で、何度も音読させられた、その癖がつい出てしまったのかもしれない。
「颯兄ぃ何それ?」
「なんだそれ颯一郎。おいらにも教えてくれ」
綾子はあきれ、お父さんは興味津々である。
「春と修羅の序・・・・・・」
「はるとしゅらあ?」
「うん、宮沢賢治のね」
綾子はあっけに取られている「颯兄ぃが頭よさそうになってる・・・・・・」
お母さんも洗い物の手を止める。
「颯クン、塾でそんなお勉強しているの?」
「いや、これはその・・・・・・授業の始めに音読課題があって、毎月変わるんだ」
お父さんが、にやにやしながら颯一郎とお母さんの顔を交互に見ている。
「お母さん、黒縁塾って、『おいらたち』の想像より、ずっといい店かもだよ」
「店って、料理屋じゃないんですよ」
「なんとなくだよ。中卒で学のないおいらだけど、おもしろいにおいがする」
颯一郎のお父さんは、中学を出てから料理一筋でやってきた人である。
今はこつこつためたお金で、町内のつぶれたラーメン屋を買い取って、自分が開店するための店に改装中なのであった。
「中卒で学のないおいら」が口ぐせのお父さんだが、ときどきこうやって言い切るときがある。
「で、その 春としゅらっての 意味を教えてくれよ颯一郎」
無邪気に聞いて来るお父さんに、颯一郎は思わず口ごもる、
「あ、ええと・・・・・・意味は、分からないんだ」
「なんだ。ただ格好つけただけ? っていうか颯兄ぃ、中二病っぽい」
綾子がからかう。
「中二病じゃねえし。でこは黙ってろ」
綾子のことを「でこ」と呼ぶときは、ふざけているときか、言い合いしているときのどちらかだ。
「でも、その塾、なんだか気になる~」
綾子が、「でこ」と呼ばれたことをスルーして塾の話を続けるのが、颯一郎には意外だ。
いつもなら「でこって言うな!」と突っかかってくるのに。
颯一郎は一旦、冷静になる。
「なんで?」
「だって、なんか学校と関係ない勉強ばっかりしてそう」
「そ、そんなことねえし」
言いながら、颯一郎はちらりとお母さんに目をやる。
お母さんは、また洗い物にもどっていて、その表情は読めなかった。
そういえば、家でお父さんやお母さんに「塾でこんな勉強した」のようなことを詳しく話したことは、なかったかもしれない。
颯一郎と綾子が二階に上がった後のリビングでは、お父さんとお母さんがまだ話をしていた。
「いやあ、明日は楽しみだ。黒縁先生、きっといい人だ」
お父さんは、楽し気にビールを飲んでいる。
「また、そんなこと言って。会ったこともないのに、分かるわけないでしょ」
この家の中での一番の常識人はお母さんだ。このお母さんの存在によって、この一家のバランスは保たれている。
「分かるさ」
もう何度も夫婦で似たような会話を交わしてきたのだろう。お父さんが次に何を言うかはお母さんにも分かる。タイミングもぴったりに、二人の声が同時に響いた。
「プロだから」
(つづく)