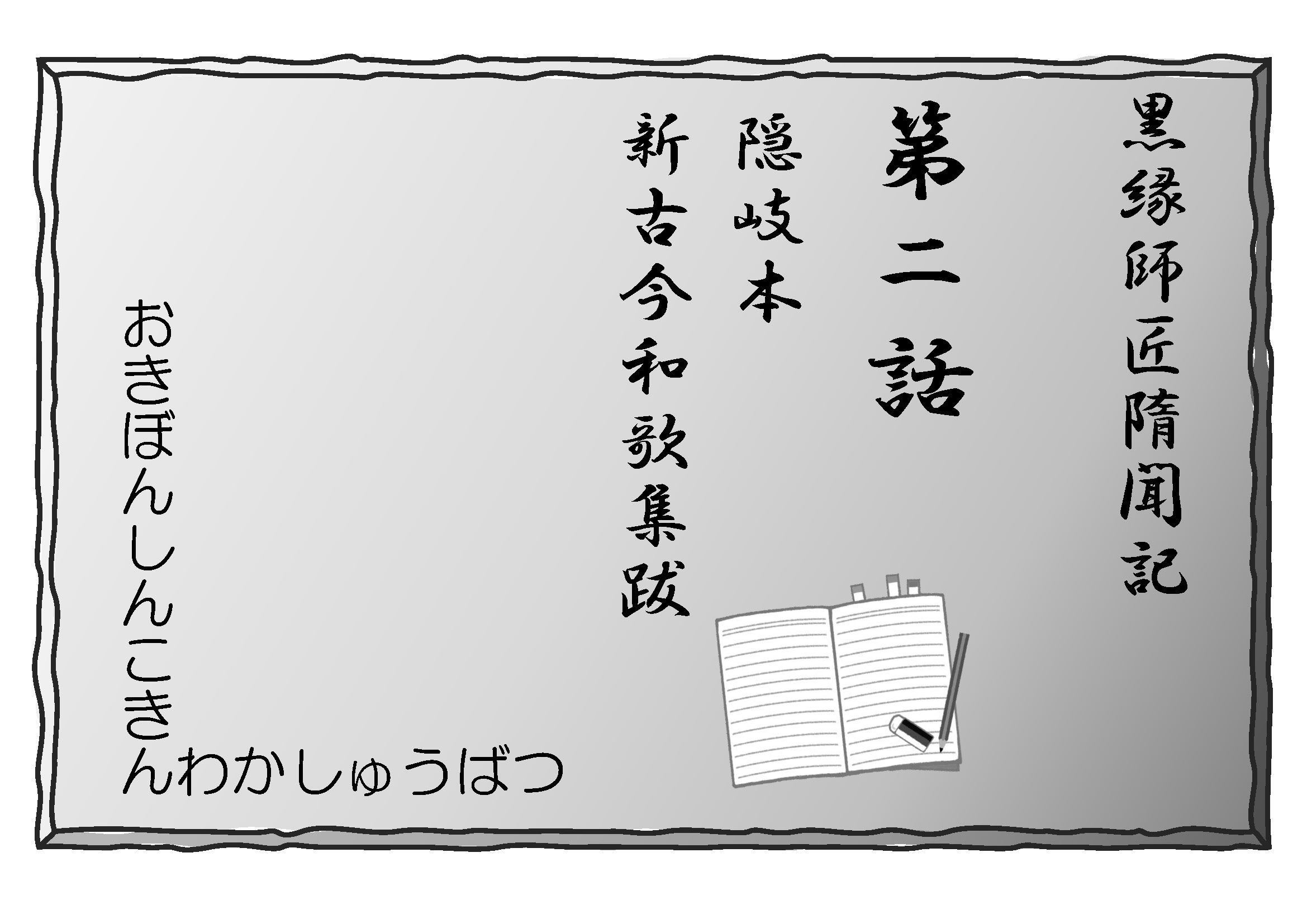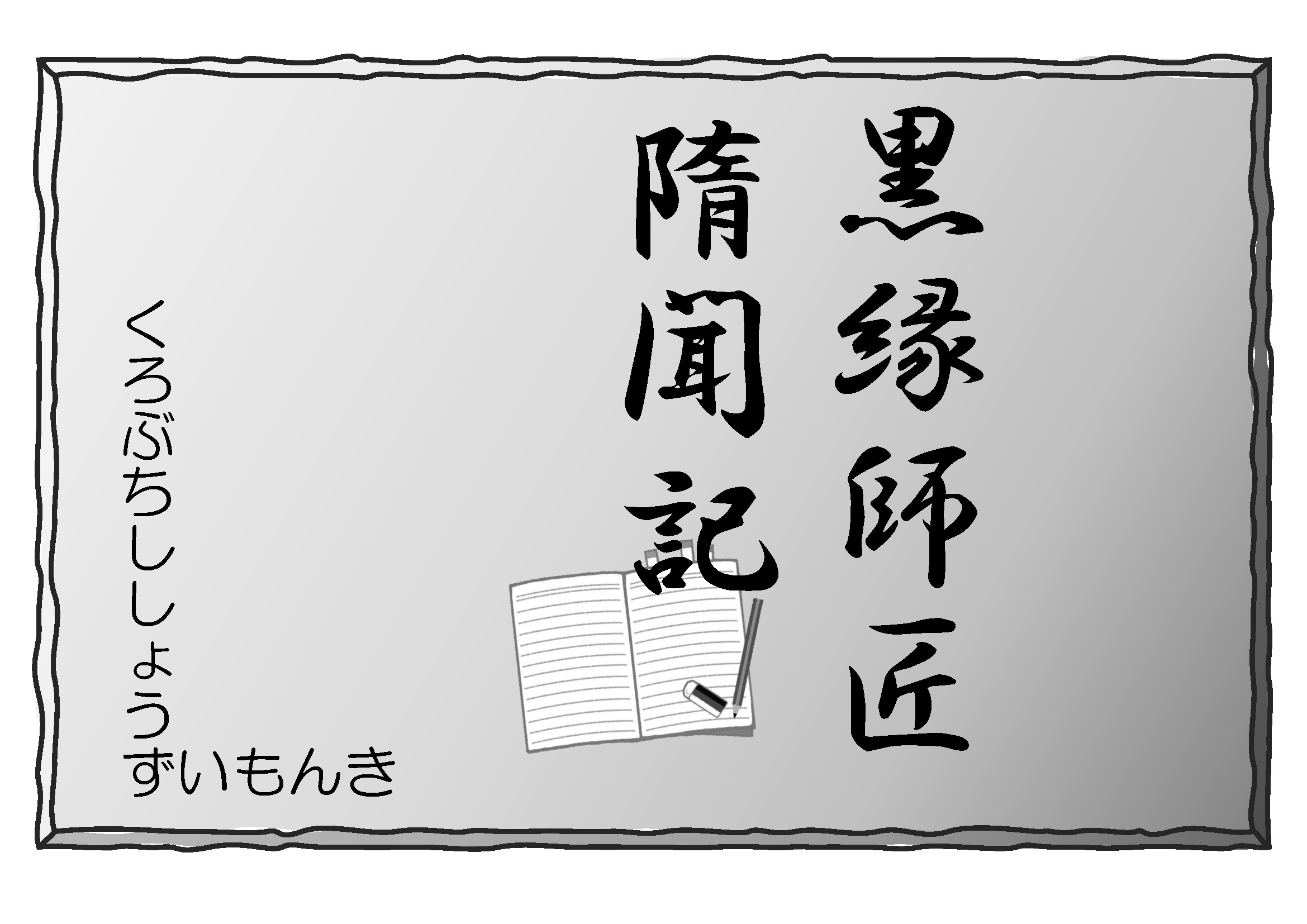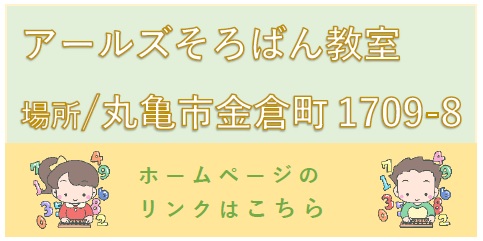「はい、時間。おしまーい。帰りまーす」
黒縁先生がダルそうに言って、そそくさと帰り支度を始めた。
「ちょ、先生!まってよ。あと少し、お願いします」
颯一郎は、まだ解きかけの因数分解の問題と黒縁先生を交互に見ながら、懇願する。
「先生って言うな!師匠やろが!師匠!もっかい『先生』って言うたら罰金1億円な。それより、はよしまえや、教室閉めるぞ」
ここは、とある田舎町の学習塾である。
『黒縁塾』
という、テナントビルの二階にある小さな学習塾に颯一郎は通っていた。
中学3年生の颯一郎は、中1からこの教室に通っている。
颯一郎を入れて、中学生はニ三人しかおらず、中3は颯一郎一人である。
この日、金曜日は中3だけの日なので、夜の8時を回った教室の生徒は颯一郎だけとなるのだ。
実は、颯一郎はこの日を楽しみにしている。
「たまに」なのだが、授業が終わった後、黒縁先生の「気が向く」と、勉強とは関係ない話をしてくれるのだ。
颯一郎はその時間が好きだった。
「せんせ・・・・・・、いや師匠!でも、おれの因数分解がまだ途中です」
「ああ? 因数分解なんざ、犬にでも食わせとけや。それより今日の晩飯は湯豆腐やねん。はよ帰らせてくれ」
「湯豆腐? せん・・・・・・師匠は湯豆腐が好きなんですか?おれ、うまいと思ったことないし」
「ふふふ、若いのう、颯一郎。湯豆腐なめとったらあかんで。豆腐、水、醤油、昆布・・・・・・。すべて1級品で行う湯豆腐ほどええもんはないぞ。『目に見えぬ鬼神』でもよだれをたらすレベルや」
(目に見えぬ鬼神・・・・・・?たぶん、これは古文の一節だ。もしかしたら、チャンスかもしれない)
そう思って颯一郎は黒縁先生の言葉を繰り返してみた。
「目に見えぬ鬼神・・・・・・って何ですか?」
颯一郎の言葉を聞いた黒縁先生は、しばらく間を置いて、ちらりと時計を見て、そして颯一郎に向き直る。
「あぁ……のな・・・・・・。『古今和歌集仮名序』や。ああもう、はよ帰りたいからちょっとだけやぞ」
「やった! 師匠! また話してください」
嬉しそうな颯一郎の顔を見て、黒縁先生は話し始めた――
やまとうたは、人の心を種として、万の言の葉とぞなれりける。
世の中にある人、ことわざ繁きものなれば、心に思うことを、見るもの聞くものにつけて、言い出せるなり。
花に鳴く鶯、水に住む蛙の声を聞けば、生きとし生けるもの、いずれか歌をよまざりける。
力をも入れずして天地を動かし、目に見えぬ鬼神をもあはれと思はせ、男女の中をも和らげ、猛き武士の心をも慰むるは歌なり。
とまあ、これが古今和歌集仮名序の冒頭部分やが、これを書いたのは紀貫之や。
で、紀貫之というのは、いろいろとすごい人で、わしに言わせると世界最古の「ネカマ」やな。
「ネカマ」って分かるような。ほら、アバターゲームとかで、本当はおっさんやのに、女の振りとかしてるやつ。
紀貫之という人は、和歌がめっちゃ得意なおっさんや。
当時、平安時代の中頃は、和歌はひらがなを使ってたんやけど、公文書は漢文やった。
そういうわけで、男性は漢文――「真名」っていうんやけど、「真名」を使うのが当たり前で、「仮名」つまりひらがなを使うのは、なよなよしとる、女のすることや、みたいなイメージがあったわけや。
「男子たるもの、ごつごつとした漢文で書けや」という世の中や。
そうやなあ……今で言えば、男子がスカートはいてたらなんかおかしいやろ。そんな感じに似てるかなあ。
でも、男子がスカートはくのに、似てるっていうても、実はちょっと違って、
当時は猫も杓子も和歌を詠むのが「たしなみ」やったから、男性でも和歌を詠むときは当然「仮名」を使う。
和歌を詠むときだけは、男子も「仮名」使うのはしゃあないという空気や。
まあ、これだけやったらよかったんやけど、ほら平安時代と言えば、女流作家がようけ出てくるやろ。
紫式部に、清少納言に、なんちゃらなんちゃらいうて、女どもがこぞって日記を書きよる。
で、その日記というのが、女性やから「仮名」で書かれているわけや。
男性が日記書くときは、漢文で書かなあかんのに、女性は「仮名」で好きなように書きよる。
たぶん、紀貫之はそういうの見て
「ええなあ……自分も「仮名」で思い切り好きなように文章書いてみたいな」
とうらやましかったんやろな。知らんけど。
まあ、紀貫之が「ネカマ」になって、土佐日記が書かれたのはこの古今和歌集仮名序が書かれたずいぶん後やけど、実は日本の公文書が「仮名」で書かれたのは、この古今和歌集仮名序が最初や。
その後、土佐日記を仮名で書く。
でも、世間的には、まだまだ「男は漢文」という空気やったから、紀貫之も
男もすなる日記というものを、女もしてみむとてするなり
と、ばればれなんやけど、一応女が書いたという体で、土佐日記を書いたのや。
だから、もし、紀貫之がおらんかったら、わしらは未だに「男は漢文」という世界線でおったかもわからんのや。
だから、すべての日本男子は紀貫之に感謝せなあかん。
ということで、紀貫之に関しては、これくらいや。
もう一つだけ、話しとくとするなら。古今和歌集仮名序冒頭の二段落目やな。
これはしれっとすごいことが書かれている。
力をも入れずして天地を動かし、
目に見えぬ鬼神をもあはれと思はせ、
男女の中をも和らげ、
猛き武士の心をも慰むるは歌なり。
ここには、「歌」の持つ根源的なパワーについて書かれている。
分かりやすく言うと、
「力を使わずに天地を動かす」
「鬼や神様の心に感動を呼び起こし」
「男と女が仲良くなり」
「荒くれ者の武士の心を安らかにする」
こうした力が歌にはある、と紀貫之ははっきり述べている。
これを、たとえ話でもなんでもなく、本気で書いてるのやとしたら、すごいと思わへんか?
歌を詠むことで、「力は使ってないけど、天地を動かす」ことができる。
できると思う?
ちょっと現代人の感覚では、分からへんよね。
でも、紀貫之はそれが「できる」と考えてるんや。
そして、日本で最初の勅撰和歌集である、「古今和歌集」の「仮名の序文」でもって、
「おまえら、歌にはこういうパワーがあるんやぞ」
って言い切ってるんや。まあ、すごい。
現代の日本政府が、公式見解で
「歌には天地を動かす力があります」
と言っても、誰も信じないよな。
でも、当時は堂々とこれが採用されたということは、たくさんの日本人にこの言葉が受け入れられる文化的背景、「なるほど」と思ってもらえる共通認識があったということになる。
歌というのは、元々は祈りや。
その祈りに関して、たくさんの日本人は、
「そんなん、天地を動かすこともあるやろ」
と信じてたということや。どや、すごいやろ。
ああ、あかん、もう8時半過ぎとるやんけ。
はよ帰って、湯豆腐や。
今日はここまでや、颯一郎。また今度な――
帰り際に、颯一郎は黒縁先生に食い下がってみた。
「じゃあ、師匠。おれも和歌を詠んだら、天気を変えたりできます?」
カバンにiPadやUSBメモリを詰めながら、黒縁先生が答える。
「天気なあ・・・・・・」
黒縁は、教室の奥半分の電気を消し、カバンを手にすたすたと出口に歩いていく。
「ちょ、師匠! 待ってください」
颯一郎は、黒のリュックサックを肩にかけると、靴をはいてドアの外に出て黒縁に挨拶する。
「さようなら」
「颯一郎、わしに挨拶はええねん、あっちや」
黒縁が教室の奥にある神棚を指差す。
「あ、今日もありがとうございました」
颯一郎が、神棚に向かってちょこっと頭を下げるのを見届け、黒縁が教室の電気を消して、ドアを閉めた。
二人が、前後に並んで階段を下りる。
「颯一郎。天気を動かすのは、やめとけ」
「なんで? おれ、雨きらいやし。雨ふるのを止めれたらいいなって」
「雨を嫌うのは人間だけや」
「先生、でもおれ人間ですよ」
「ふっ・・・・・・」
黒縁先生が、笑っている。
この先生は、こうやって会話を終わらせることが多い。
もっと、何かコメントしてくれたらいいのにと、颯一郎はよく思う。
やがて二人は、建物脇の自転車置き場まで来ていた。
白いマウンテンバイクが一台あって、それが颯一郎の自転車だ。
「今日は雨じゃなくてよかったな」
駐車場へすたすたと歩いて遠ざかりながら、黒縁先生はこちらに顔を向けることもなく自分の車に向かっていった。
先生の言う通りだった、颯一郎の頭上のビルのすき間からは、白鳥座のはしっこかもしれない星が見えていた。
(つづく)