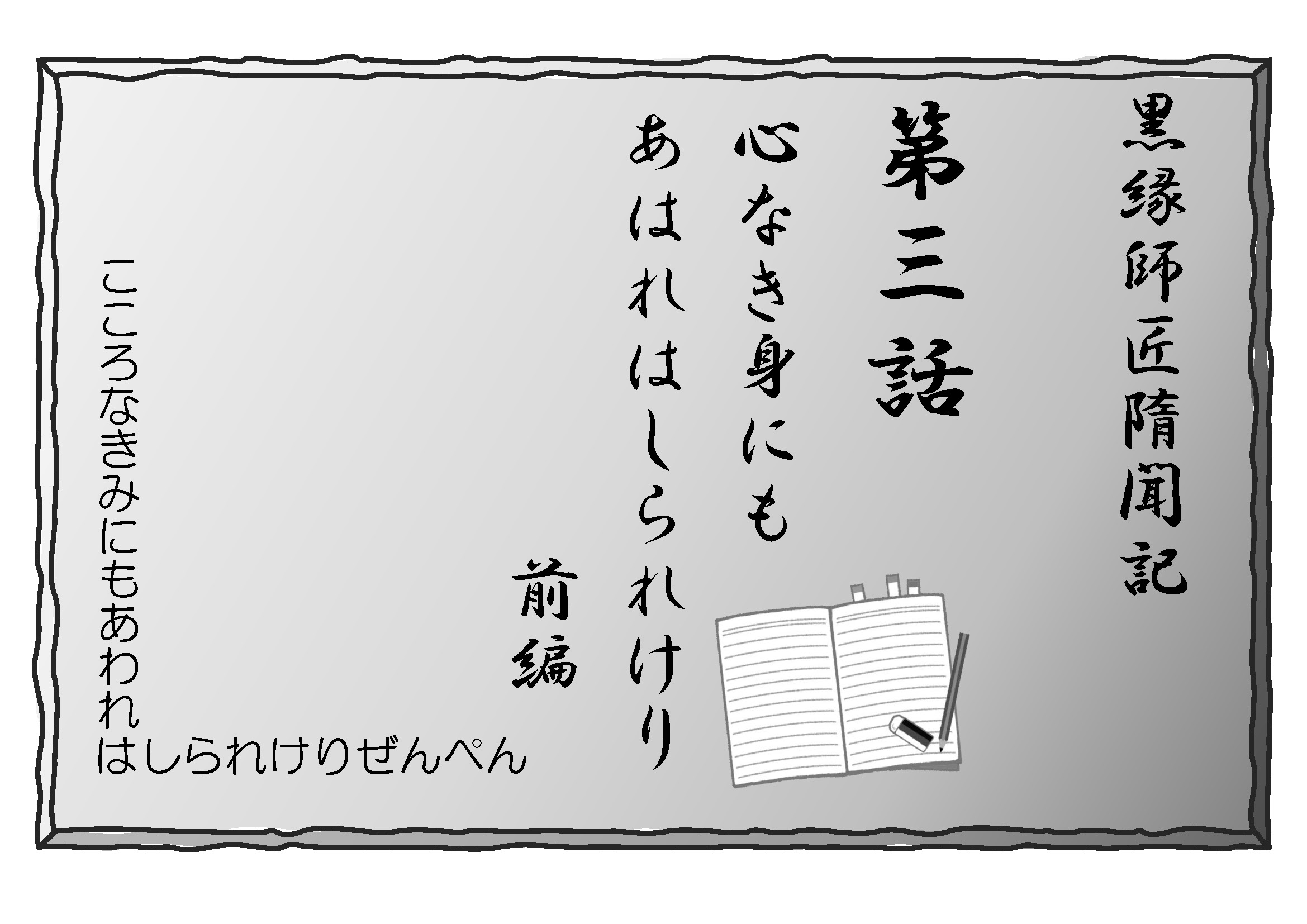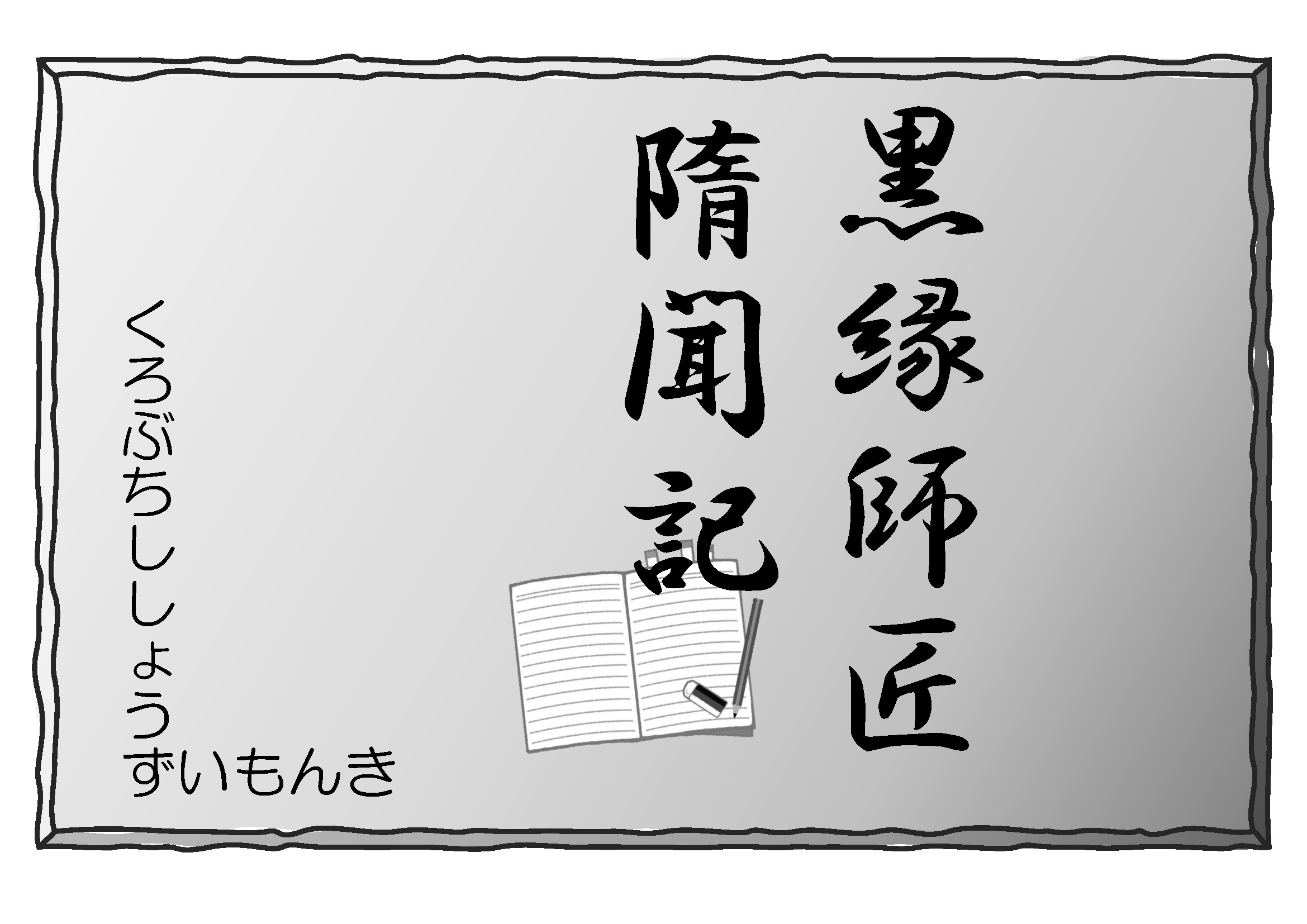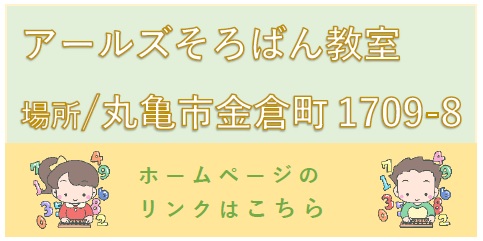「颯クン……もう塾変えた方がいいんじゃない?」
三者懇談会があった日の夕食時、お母さんにそう言われた颯一郎は、すぐに言葉を返すことができなかった。
黙々と、お母さんの小言に句読点を打つように、颯一郎はカレーライスを口に運ぶ。
中学3年になって初めての三者懇談で、颯一郎の担任の先生は颯一郎親子にこう言った。
「このままの成績では、公立では行く高校がありませんねえ。颯一郎君は、部活をがんばっているらしいですけど、スポーツ推薦を受けられるほどではありませんので、やはり一般入試で進学するしかありません。5教科全体的にあと3、4点ずつでもいいから、伸ばしてくれたら・・・・・・」
「行く高校がない」という先生の言葉が、よほど刺さったのか、
普段は勉強のことをまったく話題にしないお母さんも、さすがにこのままではいけないと思ったようだ。
颯一郎は、やはり黙ってカレーを食べ続ける。
「颯クン、ビシバシ塾の体験学習、行ってみる? あそこはお金かかるけど、お母さん頑張るから」
ビシバシ塾の名前を聞いた颯一郎は、(それだけは勘弁)と思った。
宿題も多い、拘束時間も長いビシバシ塾に行くなんて、想像するだけで寒気がする。
そこで、ちょっといいことを思いついたとでも言いたげに、颯一郎が口に運ぶスプーンの手を止めると、
「お母さん、ちょっと待って・・・・・・」
両手の指を折りながら、口の中でブツブツ何かを言い始めた。
「できた!」
すると颯一郎は、お母さんの方に顔を向けて、ゆっくり唱え出した。
「成績を 上げる決意を 今したよ 塾はこのまま 行かせてください。よっしゃ、カンペキ!」
言い切って、嬉しそうにしている颯一郎を見て、お母さんはあきれてしまった。
「なにそれ?」
「『やまとうた』だよ。すごいパワーがあるって、先生が言ってた」
「相変わらず変な先生ね……そんなことより、次の模擬試験で少しはましな結果を出さないと、困るのはお母さんじゃなくて、颯クンなのよ・・・・・・」
お母さんが、心配そうにため息をつくのも無理もないことだ。懇談のときの担任の先生とのやり取りがよみがえる。
「先生・・・・・・たとえば、三重津工業に受かるためには、ここから何点くらい上げないといけないでしょうか?」
不安げに聞くのは颯一郎のお母さんだ。
「そうですね。前回の入試型5教科テストの合計が80点でしたが、まあ、内申点から見て、あと30点は伸ばしたいところです」
「そんなに・・・・・・」
入試型5教科テストというのは、中学3年生になると、県下一斉に行われる公立高校入試の模擬テストだ。
配点は1教科50点、合計は250点満点で、中学3年生のあいだに何度か実施される。
その点数をもとにして、みんな自分が受験する高校を決めるのだ。
入試本番では、底辺の公立高校でも90点は必要と言われているが、颯一郎の合計点は80点なので、今のままだと合格できる公立高校はほぼない。
颯一郎の住む県は、それほど都会ではないので、都会のような私立指向とは真逆で、大多数の中学生は、公立を第一志望とし、私立は「公立にすべった人が行くところ」というイメージが定着していた。
担任の先生は言う。
「たくさん生徒を見てきましたが、中3の春の成績から、入試本番に向けて、飛躍的に成績を伸ばす生徒はまれです。ほとんどの生徒は、だいたい春に取った成績のまま、本番まで推移します。ここから30点伸ばすとなれば、颯一郎さんにとっては、大きな挑戦になります。私の意見では、これまでと同じではいけないでしょう。大きく何かを変える必要がありますね――たとえば、勉強時間も含めた生活習慣を変えるとか、塾を変えるとか――あくまで個人的な意見ですが。ところで、ずっと黙っているけど、颯一郎さんはどう思いますか?」
ふられた颯一郎は、「え」と顔を上げて、抑揚のない声で、
「ええと・・・・・・三重津工業に行きたいです」
とだけ言った。
「じゃあ、まずは社会を頑張らないとですね。1桁得点では話になりません」
そうであった。
前回テストでの颯一郎の社会の点数は、50点満点中、たったの6点だったのだ・・・・・・
「せんせぇ~」
急に、颯一郎が情けない声を上げて、黒縁に助けを求める。
苦手教科だらけの颯一郎であったが、その中でも歴史は特に苦手である。『〇〇の乱』と言われてもわけがわからない。
今、颯一郎は、承久の乱のことで黒縁に分かりやすく教えてもらいたかった。
「なんやお前、『せんせぇ~』はこの部屋におらんぞ。おるのは『お師匠様』だけや」
黒縁塾の金曜日。
時計は7時30分を指していた。
教室は、たくさんいた小学生たちがすでに退室し、残る生徒は中3の颯一郎のみとなっていた。
「というか、師匠。携帯ばっかり見ないで、おれの勉強も見てくださいよ」
「ムダや」
「なんでムダとか言うんですか。ふつう、塾の先生って勉強見てくれるじゃないですか」
「あ?」
黒縁が、メガネを中指でクイッと持ち上げて颯一郎をにらむ。
もちろんメガネのフレームは黒縁だ。
「あのなあ、勉強みろって、『はいは~い。そういちろうちゅわーん、てんてーといっしょにお勉強ちまちょーねぇ』とかやれってか? わしがいくら、お前に手取り足取り『あーやこーや』とやっても、結局それはお前の身にはつかへん。お前は『勉強したつもり』になるだけや。自分で壁にあたって、その壁の前で『どうやったらこの壁超えられるやろか』とあれこれやってみるのが本物の勉強や。何度も言わすなやタコ助」
いつもの黒縁先生のお説教である。
颯一郎はそろそろこのパターンを聞き飽きてきたので、別の角度で黒縁先生をいじってみようと思う。
「ところで、せん・・・・・・師匠は今何を観てるんですか?」
「タイガースや」
「え、タイガースって、野球の・・・・・・ですか?」
「そや、タイガースの1球速報観てるんや。文句あるか?」
「それって、塾の先生が、授業中にタイガースの中継観てるなんて、普通の塾だと炎上しますよね? ふつうは、生徒に勉強教えるのが塾の先生の仕事ですよ。」
「せやから中3はお前ひとりしかおらへんやんけ。なんや、そんなに勉強したいなら、うちなんかやめて隣の『ビシバシ塾』でも行ったらええやんけ。授業もやってくれるし、宿題もようさん出してくれるぞ。おお、また三振とりよった。すごいなこのピッチャー」
変な塾だと颯一郎も思う。
こんな黒縁の姿、お母さんに言ったら「やっぱり、すぐにそんな塾やめなさい!」と言われるに決まっている。
しかし、颯一郎はこの教室を絶対に絶対にやめたくない。
「でも……師匠、あの、ちゃんと儲かってるんですか?この塾つぶれたら、おれ困るんですけど」
颯一郎の言葉を聞いて、黒縁先生は携帯を閉じて、視線を颯一郎に向けた。
「なんやお前、わしの懐具合を心配してくれてんのか?」
「心配っていうか……ほら、車もずっと軽だし」
「心配せんでも、もう三十年首の皮一枚で通してるわい。ちなみに、今日の晩飯は和牛のステーキや。」
虚勢なのか、本心なのか、もちろん颯一郎には判断しかねる。
でも、これだけは確かだ。この黒縁先生という人は、いつも常識とは真逆のことを言う。
「お金? ある意味修業やな。結局その人の器分しか入らんようになってる」
「勉強? 好きなようにしたらええねん。まともに生きようとしたら、一生勉強することになってる」
そういう話を颯一郎はもっとたくさん聞きたいと思う。
でも今、颯一郎は話題を最初のきっかけにもどすことにした。
「というか、師匠。承久の乱って何ですか?」
「ああ? 承久の乱やと? そんなん、後鳥羽上皇対鎌倉幕府で、鎌倉幕府が勝ったんや。それだけ覚えとけ」
「師匠……承久の乱って意味分からんのですけど」
「なんでや」
「幕府っていうのは、天皇が認めるから幕府になるって、前に師匠が言ってました」
「その通りや」
「なのに、鎌倉幕府を認めた天皇が、鎌倉幕府を相手に戦ってるんですよ?」
「なるほど・・・・・・」
黒縁先生は、携帯のカバーをパンと閉じて、
「お前にしては珍しく、わしが教えたことを覚えてるようやな……」
そう言いながら、いつものように話を始めた――
後鳥羽上皇が、どれだけ民草のことを思ってたのか。そんなん知らん。しかし、建前としては、民というのは天皇にとって「おほみたから」なんや。つまり、めちゃめちゃ大事な宝ということやな。
それで、天皇がその時々の権力者に統治を委ねることで、「おほみたから」を任せる形を取ってる。
これが、長い長い日本の歴史で行われてきた、天皇と統治者の関係や。もちろん例外はある。
鎌倉幕府の場合やと、天皇が征夷大将軍を任命することによって、「おほみたから」つまり「日本国民のことはまかせたぞ、おまえにあずけたぞ」という形をとってるんや。
そしたら、征夷大将軍は「ははぁ」ってことで、天皇からお預かりした「おほみたから」が幸せに暮らせるように、あれこれ働くという、これが日本における天皇と統治者のたてつけやな。
鎌倉幕府の初代征夷大将軍は源頼朝だったわけやが、これは一応、清和天皇の血筋を引いているということやった。
当時の日本人の考えの中では、統治のトップに立つ者、この時代の場合は征夷大将軍やけれども、それは「高貴な血筋を引いている」ということは必要条件やったんや。
「なんやそれ。結局血筋かいな」と思うかもしれへん。
でも、そうでないと、戦にさえ勝てれば誰でもええんかみたいな話になるからな。
統治者になれる者の最終的な担保が、当時は高貴な血筋やったんや。
だから、後鳥羽天皇も、「源頼朝やったら清和天皇の血筋を引いているから」ということで、源頼朝を征夷大将軍に任命した。
そして、その後ろを支えていたのが北条氏やったわけや。
後鳥羽天皇かてアホやないから、実質的権力は北条氏が握ってるということは分かってても、トップに天皇の血を引いた源頼朝がいるなら、「まあええよ」ということで鎌倉幕府を認めた。
ところが、源頼朝が死んでから、三人の息子がどんどん死ぬやんけ。
それも、謀殺や暗殺や。
三代将軍の源実朝が暗殺されたことで、ついに源氏の血筋が絶えてしまった。
これは、京都から見たら、
「いやいや、お前ら何やっとるねん」
って話になるんよね。
「源の血筋があるから、幕府ってことで認めてやったし、そもそもこの国の統治の実質を北条とかいう関東の、わけわからん田舎者が握るとか、いやいやいやないないない」
ってなったんよ。
んで、後鳥羽天皇としては、「話が違う」ってなって、そのときの鎌倉幕府の執権やった北条義時を排除するしかないなあ、諸悪の根源はこいつやなあ、ってなったわけ。
それで、後鳥羽天皇は鎌倉幕府に対して兵を挙げたんやな。
でも、よう考えてみたら、源平の戦乱をくぐり抜けて、勝ち残ったのが鎌倉の連中よ。
後鳥羽天皇が寄せ集めで兵を挙げたって、そりゃ相手にならん。ということで、後鳥羽天皇はコロッと負けてしもたんや。
勝った北条からしたら、まさか皇族を殺すわけにもいかんので、隠岐に流すことになったんや。
まあ、あれや。承久の乱については、こういうことなんやけど、お前はわしの生徒やから、この後の話もちゃんと聞いておけ。
ええか、ここからが大事や。
後鳥羽上皇は、隠岐に流されて何をしたか。
それは、自分が在位中に命じて作らせた『新古今和歌集』の再編纂をしたんや。
その作り直した『新古今和歌集』に、跋文いうてな、まあ、あとがきがあるんやけど、その一節を見ようか。
玉の台やはらかなりし昔は、なほ野辺の草しげきことわざにもまぎれき。
砂の門月静かなる今は、かへりて杜の梢深き色もわきまへつべし。
ふかふかした玉座に座っていたあの頃は、いろいろといそがしくてやれないことも多かった。
ここ隠岐に流されて、月も静かな気持ちで眺めることのできる今は、かえって森の木の梢の色を見ても、その深みがよく分かる心境になっている。
という感じの意味なんやけど。この「野辺の草しげきことわざにもまぎれき」っていうのがな・・・・・・あれなんや。
古今和歌集仮名序を踏まえているの、分かるか?
世の中にある人、ことわざしげきものなれば、心に思ふことを見るもの聞くものにつけて、言い出せるなり。
ほら、シンクロしてるやろ。
この一節なんやけど、わしは初めて目にしたときに、理由はよくわからんけど結構感動したんや。
それで、「なんでわしはこの一節にこんなに心を動かされたんやろ」ってことをものすごく考えた。
この一節は、対句形式になっていて、「昔の自分」と「今の自分」を比べる構造になっているわけやけれども、
「今の自分」に関して、腐ってるところが一つもない。
京都で、天皇やって、その後に上皇までやって、世の中を動かしてきた自分。
それが、戦で敗れて、隠岐に流されて・・・・・・って、普通腐るやろ。
でも、そういう腐ったところを微塵も感じさせるどころか、
「かへりて杜の梢深き色をわきまへつべし」
って、つまり、「以前の自分には見えない景色が見えるようになった」みたいな悟りにも似た境地を告白してる。
魂が腐ってないねん。
それでもって、対句の中で「古今和歌集仮名序」の表現を踏まえているのは、明らかに意図的なもので、これは和歌の歴史に対する大いなるリスペクトやね。
「なんでわしは負けてしもうたんや」
「いやはやもう悔しいわあ」
「また京都にもどりたいわあ」
みたいな泣き言は一切なし。
今自分のいるところで、ベストな言葉を紡ごうとしたこの後鳥羽上皇の精神に、わしは感動したんやと思う――
「まあ、今日はこの辺にしといたる」
と、黒縁は再び携帯を開いて、操作し始めた。
「あちゃ~、同点になってるやん・・・・・・」
颯一郎は、颯一郎なりに、今聞いた話について考えてみた。
「じゃあ、後鳥羽上皇って、メンタル強かったってこと?」
「そうやな、たとえば、歴史上で流された人で有名なのは、菅原道真と崇徳上皇やね。それぞれ、菅原道真が太宰府に流され、崇徳上皇は讃岐に流されたのやけど、その後、二人ともめそめそぐちぐちやって、結果的に怨霊になってるからな。」
「怨霊って……こわっ」
「まあ、怨霊の話をしだすとまた長くなるから、今日は帰れ。ほらもう8時や」
壁にかかった時計を一瞬指差して、黒縁はまた携帯に目を落とす。
「師匠~、っていうかこの塾終わるの早すぎですよ!」
颯一郎は、ずっと思っていた不満を口にした。
「うるさいのう。わしは昼の2時からずっとここに座って飲まず食わずで授業やっとんねん。ブラック企業もびっくりやでほんま。これ以上授業したら死んでしまうやろが、お前はわしを殺す気か」
先生が今やっているのは授業じゃなくて「タイガースの応援」だから、全然ブラックじゃないなどと颯一郎は思ったが、なんだか馬鹿らしくなってきたので、颯一郎は大人しく帰ることにした。
「師匠は帰らないんですか?」
出口のドアの前で颯一郎が黒縁に声をかける。いつもなら、黒縁と一緒に戸締りをして、二人で同時に教室を後にするのだが、今日の黒縁は動こうとしない。
「ああ、延長戦になってな」
タイガース戦に夢中になっている黒縁を、颯一郎はちょっといじってみたくなった。
「和牛のステーキと、タイガース、どっちが大事なんですか?」
その言葉を聞いた黒縁が、
「あ!」
と顔を上げると、そそくさと携帯をしまって、すごい速さで帰り支度をして、颯一郎の立つドアの前まで来た。「電光石火の早業」という言葉が颯一郎の頭に浮かんだ。
「颯一郎、お前天才や。ステーキのこと、すっかり忘れてたわ。ありがとうありがとう」
教室の電気を消し、ドアにカギをかける黒縁に声をかける
「師匠、肉が好きなんですか」
「そうやな。男子たるもの、肉は基本やろ」
「ええ、おれは魚の方が好きなんだけどな」
「颯一郎は子供の割には食べ物の好みがしぶいのう。まるで料理人の子みたいや」
「え、おれ、料理人の子ですよ。せ・・・・・・師匠、知らんかった?」
それを聞いた黒縁の声のトーンが、一段上がった。
「えええ? まじか! 店はどこや? 今度食べにいくで」
「それが、今、店を作り中なんです」
「そっか・・・・・・残念や」
「完成したら教えますよ」
颯一郎に言われて、黒縁は嬉しそうに顔をほころばせて
「約束やぞ」
と言いながら、駐車場の方へ去って行った。
本当に、食べ物とタイガースのことしか頭にない人なのかもしれない。
でも颯一郎にはそのことが、おかしくてたまらなかったと同時に、このままこの塾に通いながら成績を上げることなんて本当にできるのだろうかと、心配になった。
(つづく)