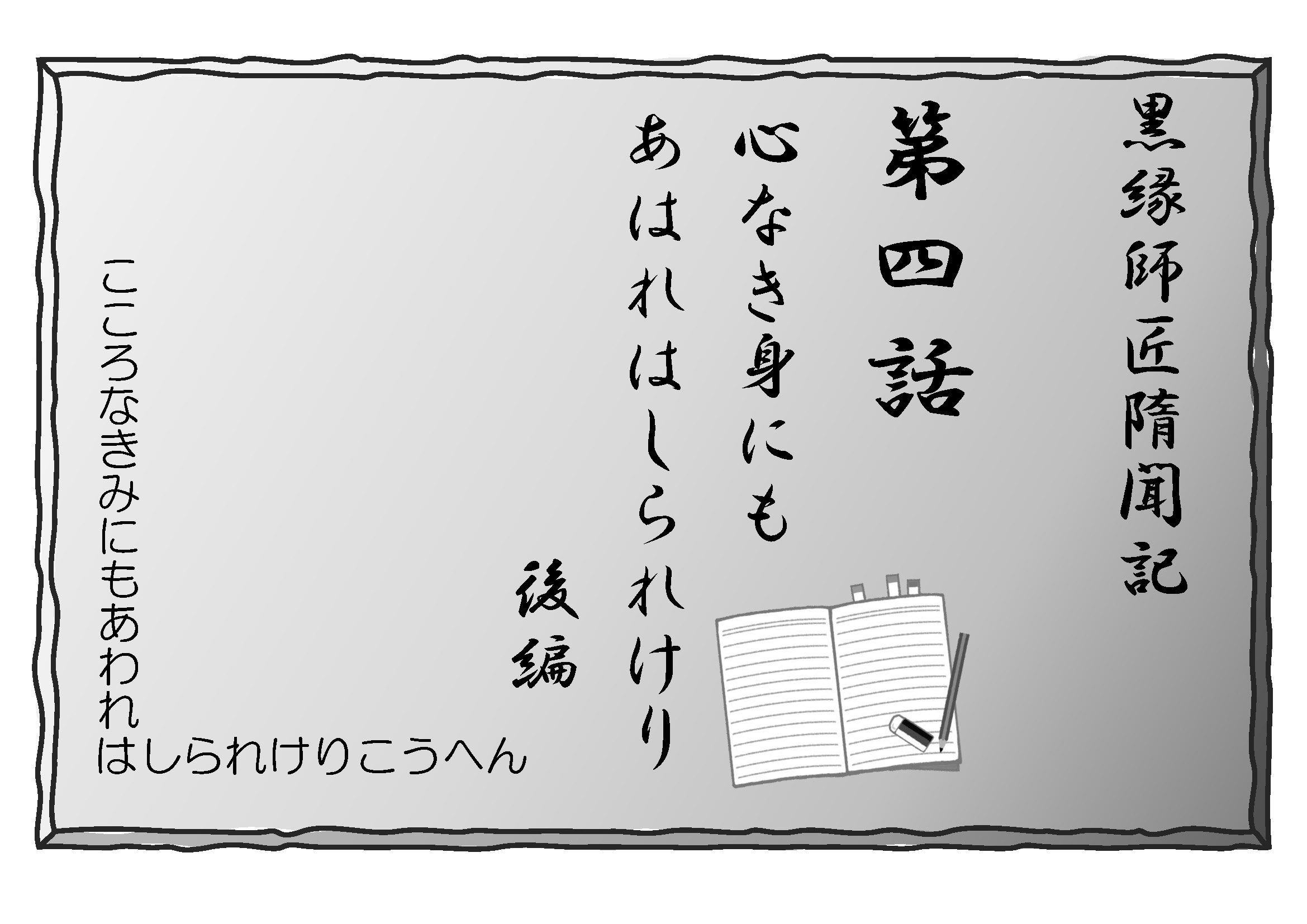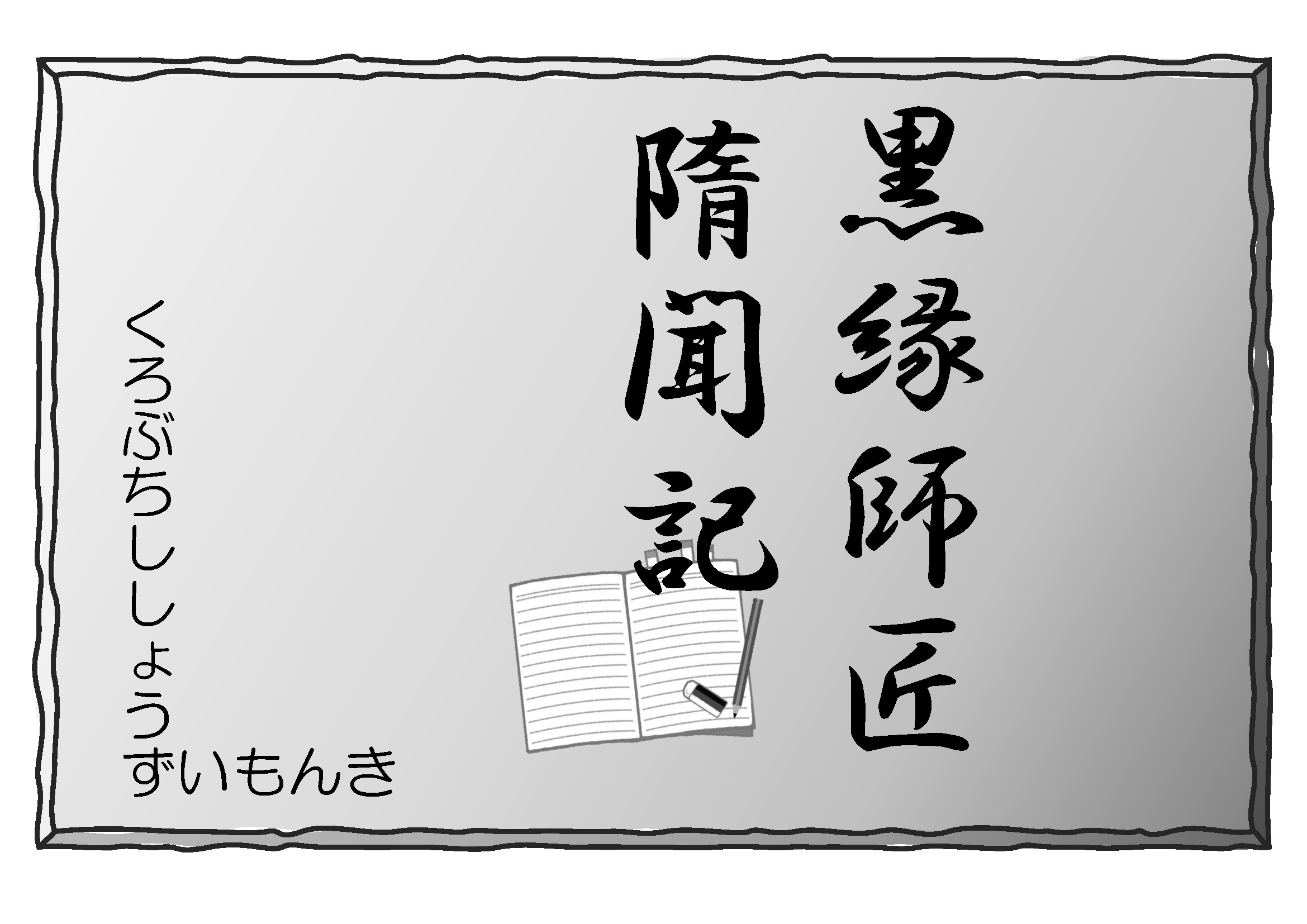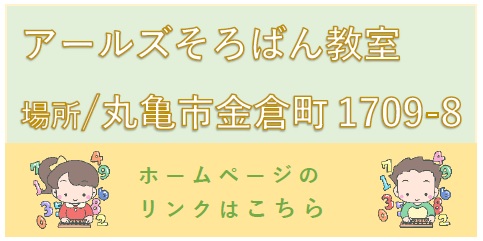颯一郎にとって、「先生」という存在は自分を何かに縛り続ける存在でしかなかった。
小学校のときもそうだし、中学校になってもそうだ。
特に尊敬できるような点がないにもかかわらず、自分に何かを押し付けてくる。
宿題もそう、勉強もそう。
「あれをするな」「これをするな」と言って、行動に制限をかけてくる。
そうかと思ったら、
「あれをしろ」「これをしろ」と言って、やりたくもないことをさせられる。
そして、その理由を説明することは、絶対にないのだ。
「なぜ、しなくてはならないのか」または「なぜ、してはいけないのか」
こういった疑問を『先生』という種族にぶつけることを、颯一郎はあきらめていた。
「そういうものだから」
「みんなそうしているから」
どうせこんな答えが返って来るに決まっているのだ。
中1のある日、お母さんが突然、颯一郎に塾を勧めて来た。
「いい先生がいるらしいよ」
お母さんは「いい塾」とは言わなかった。
初めて黒縁塾に行った日、教室では黒縁先生と数人の中学生が勉強していた。
黒縁のメガネをかけた、白髪交じりで、がたいのいいおっさんが、にこにこしながら
「まあ、自習教室に毛が生えたような教室だから。好きなようにやりな」
とだけ言って、他は特に何も聞かれることもなく、その日の終業時間になった。(というか、その終業時間が夜の8時って、終わるの早すぎない?)
かなり緊張していた颯一郎は、肩透かしをくらった気分だった。
「今どんな成績?」とか
「得意教科や苦手教科」とか
「志望校」とか、
色々聞かれるものと思っていたのだが、その手の質問は全くなかった。
唯一聞かれたことと言えば、
「お前って、ジャンプ読む?」
だった。
一応、チェックしている連載があったので、
「はあ、まあ、一応・・・・・・」
と答えたら、
「やったぜ。最近の若けぇ奴らはジャンプ読まねえんだよ。話が合わなくていけねぇ」
と、なんだか江戸っ子みたいな口調になっていた。この人は、嬉しくなると江戸っ子になるのだろうか?
他にも気になることはいくつもある。
勉強に関することは何も聞かれなかったし、何よりも、いきなり「お前」呼ばわりしてきたことに、少し衝撃を受けた。
最近の塾は、生徒を「お前」って呼んだり、「アホ」とか「バカ」とか言ったりしなくなった、言ってはいけなくなった。
そんなことをまだやっている塾は、時代遅れの、ダメな塾なんだと、耳にしたことがある。
その日の颯一郎は、何をしていいのか分からないし、黒縁先生も特に「何をしろ」のようなことを言わないので、とりあえず学校の宿題を教室で済ませて、家に帰った。
「おかえり~。どうだった?」
興味深そうに聞いてきたお母さんに、颯一郎はわざとそっけなく答えた。
「うん、あの塾に通うよ」
「え? ああ、あそうなのね。気に入ったのね。よかったわ」
(ちがうちがうちがう)
「気に入った」のではない。
「気になった」のである。
気の抜けたような塾だけど、何かあるような、そんな気が颯一郎にはしていた。
その「何か」を颯一郎は今もうまく言葉にすることはできないけれども、あれから2年経って、颯一郎はこの教室に来ることが、自分にとって大切な何かになるような気持ちになっていた。
が、同時に自分の成績に対する不安も大きくなってきた。
教室に行っても、黒縁先生は「今日何するの?」と聞いて来るだけなのである。
たとえば、「数学します」のように返事をしたら、「ふーん」で終わりだ。
「本当に、こんなの塾と呼べるのだろうか」と何度も思った。
ところで、中3にもなると、友達との会話にも受験の話題が混ざるようになる。
颯一郎には、ずっと仲良くしている友達が1人いた。陽彦だ。
こいつは勉強がめちゃくちゃ出来る奴で、学年順位が下から〇番目・・・・・・のような颯一郎とは真逆である。
しかし、なぜか分からないけど、ずっと一緒にいる。部活も同じ卓球部だった。
「で、颯一郎はどこ受けるの?」
部活が終わり、道具をかたづけながら陽彦が聞いてきた。
「うん、三重津工業。陽彦は当然東山西高だろ?」
東山西高という東だか西だか分からない高校名であるが、県内では最上位の進学校である。
しかし、陽彦ならば、スイカゲームをしながらでも受かるだろう。
「まあ、親がさあ、『司法書士になれ』ってうるさいからね……」
「他になりたいものないの?」
「わかんねえ。でもまあ、一応親も司法書士だし、金も儲かるし」
「すごいなあ。じゃあ寿司おごってよ」
「は? まだなってねえし。なってもおごらないし。それより、お前大丈夫か? おれのことなんかより、自分の心配してるのか?」
陽彦の口調が少し強くなった。
何か陽彦の気に障ることを言ってしまったのかもしれないと思い、颯一郎は胸がちくちくするような気になる。
陽彦が続ける。
「お前、あの『ブッチ塾』行ってるんだろ? 大丈夫か? あそこ」
「ぶっちじゅく?」
「そうだよ。なんか、『けふはおやすみ』とか張り紙していきなり休みになるらしいじゃん。それに、問題集も1冊も買わないって。そんな塾で大丈夫なのか?」
「はあ、(楽しいんだけどな……)まあでも、ししょ・・・・・・いや先生の説明は分かりやすくて、話もおもし・・・・・・えと、大丈夫だよ」
ここで、「楽しい」「面白い」なんて言ったら、陽彦の機嫌をさらに損ねそうで、この時の颯一郎は、それを言うのはやめにした。
「ぶわっはっはっは。『ブッチ塾』って呼ばれてるんか、わしの教室。ぶわっはっはっは。颯一郎! お前も大変だな」
黒縁が大いに受けているのを見て、(いや、大変なのは先生の方でしょ……)と颯一郎は思った。
いや、違う、この感情は・・・・・・そうだ。
「ていうか、師匠! くやしくないんですか? バカにされて」
「あ?」
黒縁は豆鉄砲にでも打たれたような顔になって、しばらく首をかしげていたが、やがて
「あああ」
と何か合点がいったような表情を浮かべたと思ったら、突然手のひらを前にかざして、目を閉じながら
「颯一郎さん・・・・・・ああ、見えます・・・・・・見えますねぇ。颯一郎さん」
「は、はい?(なんで「さん」付け?)」
「『ブッチ塾』と言って、ここをバカにしたあなたの御友人は、颯一郎さんよりもお勉強ができますね?」
「え? 師匠、すごい!なんでそんなこと分かるんですか?」
すると、黒縁はいつもの黒縁に戻って言った
「これは、占い師のテクニックの1つで、まあ普通に当たりそうなことを最初に言うのよ。だって、お前より勉強ができない人の方が少ないやん」
「あ、そっか・・・・・・」
「あ、そっかじゃねえよ。で、その友達はどんな奴やねん」
「すっごい勉強できて、東山西も余裕で、司法書士になるって」
話しているうちに、黒縁がどんどんにやついてくる。
「司法書士とかすげえじゃん。ちゃんと『なれるといいね』って言ってやったか?」
「え?」
「『なれるといいね』って言ってやるんだ。どうせ親にでもせがまれてんだろ」
「なんで分かるんですか?」
驚く颯一郎に対して、黒縁は事もなげに、
「プロだから……」
と言って、携帯に目を落とした。
「また、タイガースですか?」
「いや、読書だ」
「またまたあ」
おどけた颯一郎の眼前に、黒縁は携帯の画面を向けた。
たしかに、電子書籍である。
しかも、颯一郎にはパッと見理解不能だった、見たこともない漢字がたくさん並んでいて、そんな本を読む気によくなれるものだと颯一郎は感心してしまった。
黒縁は携帯の画面を指先でスワイプしながら、
「そいつはあれだ、まだ『気づいていない』んだよ。だからそっとしといたれ」
「『気づいていない』? 何に?」
「心なき 身にもあはれは 知られけり ってな」
また意味不明なことを言いだした。しかし、ここからいつもの面白い話がはじまるのを颯一郎は知っている。
「師匠。『心なき 身にも・・・・・・』って何ですか?」
颯一郎の質問には即答せず、数秒の間携帯に目を落としていた黒縁は
「ちっ、しょうがねえなあ。そこ座れ」
と机をはさんで黒縁の対面にある椅子を指さした――
(つづく)