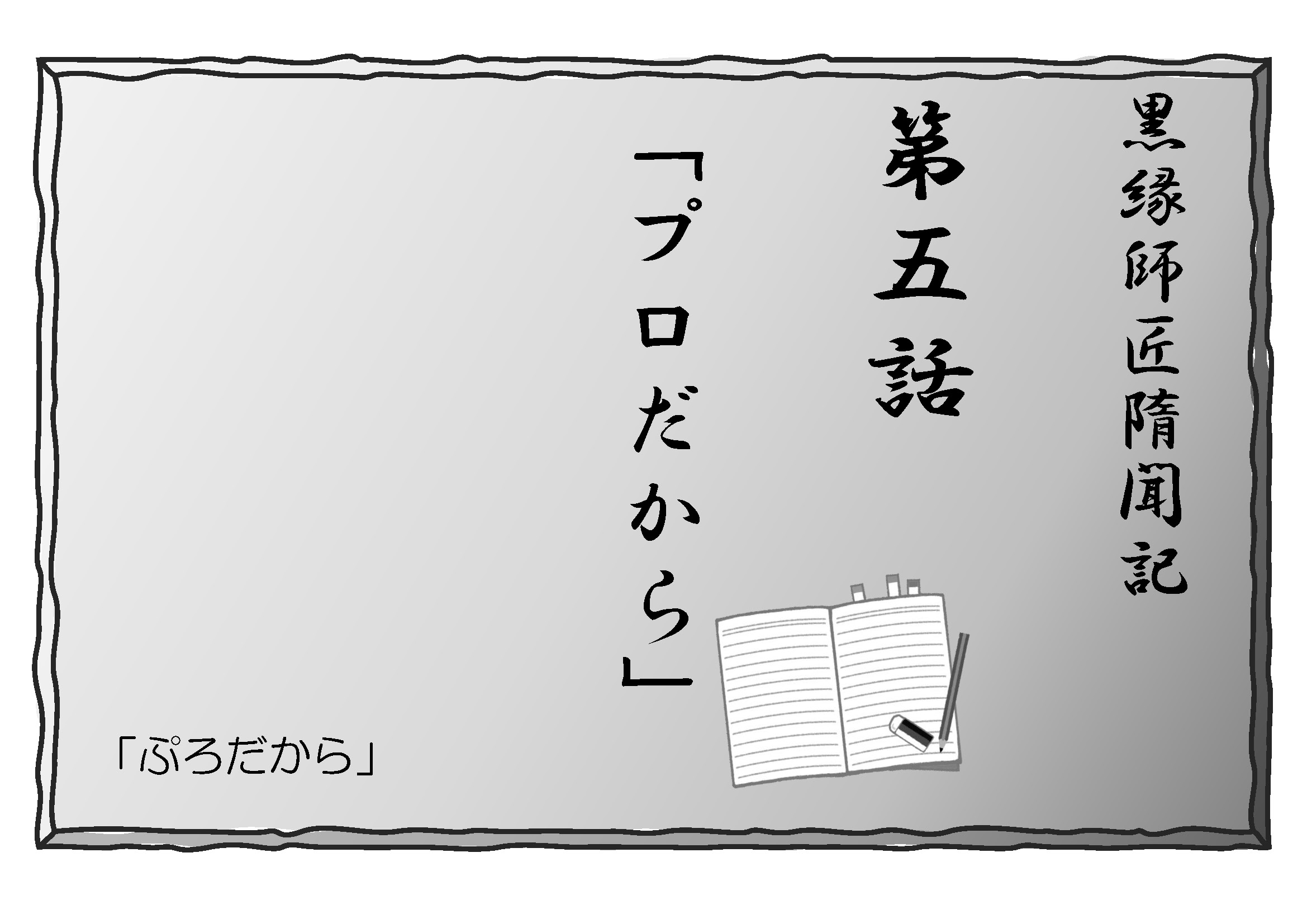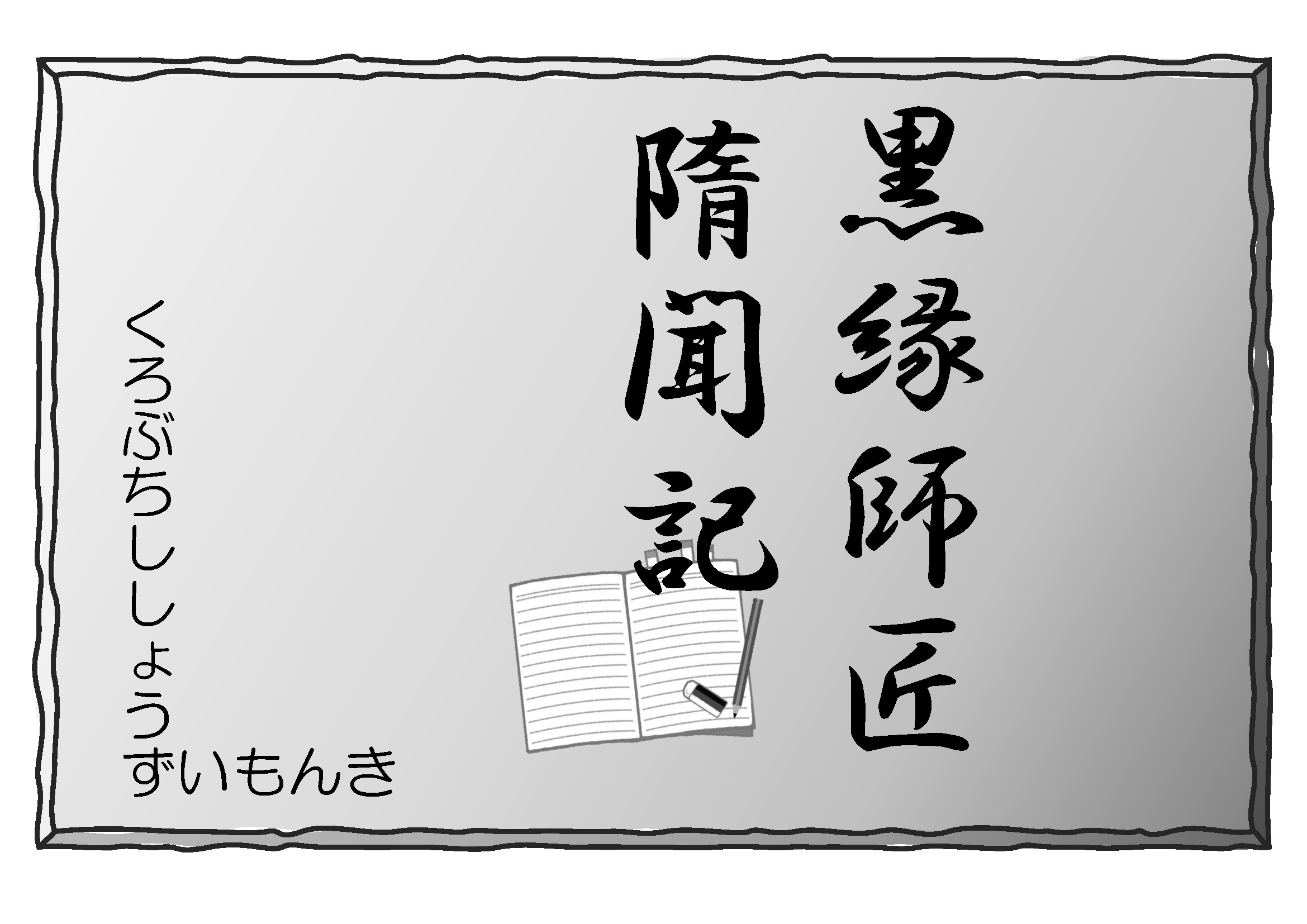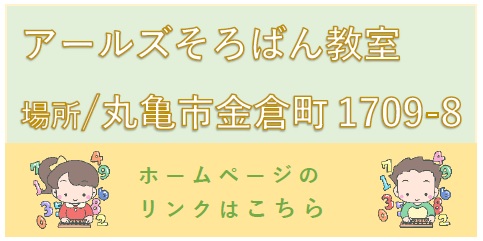――颯一郎は『三夕』って知ってるか?まあ、知らんやろから一応見せたる。
藤原定家
見渡せば 花も紅葉も なけりけり
浦のとまやの 秋の夕暮
寂蓮法師
寂しさは その色としも なかりけり
まき立つ山の 秋の夕暮れ
西行
心なき 身にもあはれは 知られけり
鴫立つ澤の 秋の夕暮れ
日本人だけでなく、人間っていうのは「3大なんちゃら」というのが好きでな。
たとえば、「三冠王」っておるよな。
落合博満とか村上宗隆とか……まあ、知らんか。
ちょっと真面目な話をすると、和歌で言うたら『三大集』というのがあって、『万葉集』『古今和歌集』『新古今和歌集』がそうや。
言うなれば「日本の3大すごい和歌集」やな。
和歌の世界に話を移すと、和歌にはいろんな定番モチーフ、ああモチーフというより、「お題」って言った方がええかな。
そんな代表的「お題」に「秋の夕暮れ」がある。
そらもう、みんなよってたかって「秋の夕暮れ」を詠むもんやから、「三大秋の夕暮れ」はどれやとなったときに、いつの間にかこの三首になってた。
なんでこれになったのかは、さっきの三大集の中の『新古今和歌集』の影響がでかいやろな。
なぜなら、『新古今和歌集』には、この3つの和歌が、並んで載ってるからや。詠んだ人も有名人やし、その辺はしゃあない。
では、この3人がどんな人か見ていく。
まずは藤原定家。
言わずと知れた『小倉百人一首』を作った人で、お父ちゃんと一緒に新古今和歌集の編纂にも関わってる。
お父ちゃんが藤原俊成というお人で、この人は平安末期~鎌倉初期の和歌の世界の中心だった。
そういう父親を持つということで、藤原定家は和歌の世界の超エリートや。
エリートだけあって、技巧もしっかりしてるし、お手本のような詠みっぷりや。
つぎに、寂蓮法師やけどな。
この人も実は藤原俊成の養子やねん。
俊成になかなか男子が生まれないので寂蓮を養子にとったんやけど、定家が生まれたので、寂蓮は出家した。
ええ? 寂蓮さんかわいそう?
わしはそうは思わんよ。
なぜなら、定家より寂蓮の方がいろいろと自由だったと思うからや。
それに、藤原俊成の元養子ということになれば、出家先のお寺でも雑な扱いを受ける心配もない。
適当に勉強して、適当に仏事をこなしとったら、あとは何してもかまわんよ、って感じやったと想像してる。知らんけど。
だから、最後の西行法師とくらべたら、同じ法師でも全く立場が違うんや。
ほな、西行法師はどんな人かっていうと、元々は下級貴族の生まれで、京都に北面の武士というのがあって、これは上皇さまの近衛兵なんやけど、そこで上皇さまの警護をするお仕事をしとったのや。
だけど、ある日突然出家しちゃう。
20歳過ぎに出家して、山の中に草庵を編んで暮らし始める。
30歳過ぎると、東北を旅したり、四国に行ったりしている。
だから、エリートの家の養子になった寂蓮や、その跡継ぎとして生まれた定家とは、そもそもの精神構造が違うと考えないといけない。
心なき身にもあはれは知られけり
意味は、
「ものの情趣を感じる心のない出家したこの身にも、しみじみとした情趣が感じられることだ」
のような解釈が一般的やけどなあ。納得がいかんのよ、わしは・・・・・・
「心なき身」というのは、「仏教の修業をしている人」とほぼ同じ意味なんや。
仏教の修業をする人は、
「この世へのすべての執着を捨てて、悟りを目指す人」
だから、やれなにが美しいだの、これこれが寂しいだの物悲しいだのと言うのは、そういうことに執着していることになる。
和歌の場合は「美への執着」やな。
「そういう執着を捨てるために、仏教の修業をしている人は、世の中のあれこれにいちいち感動しないでしょう」という意味が、この「心なき身」の中にはある。
「私のような世を捨てた仏教修行者が秋の夕暮れを見ても普通は感動しないと思われるでしょうが、それでも、ついつい感動してしまうのが秋の夕暮れだなあ」
みたいな意味になる。
しかし、これはあくまで表面的なものやね。
まず、仏教の修業の点から解説する。
「心なき身=仏教の修業をしている人」と世間からは思われているかもしれないけど、西行の場合、ちょっと違う感じがする。
なんでかって言うと、出家したものの、西行はそれほど仏教の修業には熱心ではないんやね。
ひたすら歌ばっかり詠んで、歌人として有名になっちゃって、新古今和歌集に一番沢山作品が採用されている歌人は、何と西行なんや。
西行からしたら、一応仕事やめるために『出家』という形は取ってるけど、別に仏教の修業を志すためではない。
当時たまたま、『出家』という形式があったので、その形式を採用したに過ぎない。
次の歌は、西行が出家した23歳の時に詠んだものや。
世の中を反き果てぬといひおかん思ひしるべき人はなくとも
私は世捨て人になると言っておきましょう、私の内なる思いを理解する人がたとえいなくても。
西行は「世を捨てる」とだけ言っておこう、しかし、自分の心は誰にも分からんやろなあ。
と詠んでいる。なぜ「誰にも分からんやろなあ」となるのか。
それが、一般的に想像できるものではないからやね。
じゃあ、なぜ西行は「世を捨てた」のか。
これについては、わしは西行の専門家ではないけれども、言わせてもらうとしたら、こうや。
「『社会』から逸脱し、自分に正直に生きることに決めた」
ごっつい乱暴な言い方になるけど、ざっくりまとめるとこうなるね。
別の言い方すると、「北面の武士なんぞ、やってられるか!」かもしれない。
幸い、家は上級貴族ほどではないけど、ちょっとお金持ちだから、仕事をやめたとしても食うには困らない。
まあ、当時の人々の感じを想像するに、
「仕事やめます」→「なんでやねん」→「いやだから」
というパターンは、
「ふざけんな」と叩かれたやろけど、
「仕事やめます」→「なんでやねん」→「出家するので」
というパターンやと、
「ああ、仏教の修業をなさるのですね。そらしゃあない」
と一定の理解を得られたのやと思う。
だから、西行は「出家」という形式を取った。
しかし、仏教の修業というよりは、本音は和歌の道を極めたかった。
たぶん、自分の和歌の才能にも、気づいていたと思う。
西行が出家した理由に「仏教の修業」があんまりないのやとしたら、
「心なき身」=「仏教の修業に励むがゆえに、美意識という執着を捨てた人」
というのは西行にはぴったり当てはまらないことが分かる――
「西行って、ニートみたい……」
颯一郎の言葉に、黒縁は目を輝かせる。
「颯一郎! ええ感じや! そうなんよ。今で言うニートみたいなもんや。そいつが和歌を詠んで、一躍有名になるんよ」
「ええ? だったら、仕事しながら和歌を詠んだらいいやん」
「ううん・・・・・・そうやなあ。
でも、それだと西行は、西行じゃなかったとわしは思うで。
つまり、仕事をやめた理由もいろいろ考えられるけど、『北面の武士』ってことは、戦争になったら人を殺さなあかんやん。
いうなれば、軍隊の兵士やったわけで、そしたら、普段から刀を腰に差して、弓の練習もして、みたいな毎日や」
「うわあ、なんか嫌」
「そやねん。親もそういう仕事やったから、西行も普通にそういう仕事をすることになったんやけど、
『親がそうやから、自分もこの仕事してるけど、なんか違うなあ』
みたいな感じは、あったんやろな。なんていうの?
『お前ら、仕事やからって、北面の武士やっているけど、ほんまにそれでええんか?』
というのは、西行の中に絶対あったとわしは思ってる。
当時、平安末期って、全然平和な時代じゃなくて、日本中のあちこちで戦乱があったんや。
考えてみい、坂上田村麻呂の時代からずっと日本人同士で殺し合いしてるんやで。
ずっと戦乱の世の中なものだから、そこに生きる人々も『そういうもんや』って感覚がバカになってたのかなとわしは想像してる。
でも、客観的に見たら、絶対におかしいんや。
『日本人同士でそんなに殺し合いするなや』ってわしなんかは思うわけや。
西行で言うたら、他のまわりの人が何の疑問もなく与えられた仕事をしている中で、
『いや、なんか違うくね?』っていう感覚があったんやと思うで。
こういうことは、時代に関係なくあるんやねぇ――
それと、もう一つ大きなことがあって、それは「西行の歌が、他の人と全然違う」ということや。
これは新古今和歌集を見るとよく分かる。
西行の歌ばっかりを、ずっと見てると『ああ、まあ、西行やしそうやなあ』みたいな感じで、感覚がバグるんやけど、
新古今和歌集って、当たり前やけど、他にもいろいろな歌人がいるんや。
それを順々に見ていく中で、西行の歌になると、『なんやこれ?』ってびっくりすることが多い。
なんかね。
頭一つどころか、一人だけ別世界に行ってるみたいな歌やねん。
他の人の歌は、やれ『源氏物語』だの、『伊勢物語』だのを下敷きにして、オマージュ合戦やってたり、
かと思えば、月見てわびしいだの、秋の風があわれだの、恋人が来なくて寂しいだのとかやってるようにしか見えなくなる。
その中で、西行だけは、そういうものから一切離れたところで、
しかも技巧的なこともほとんど用いずに、なんかすごい歌を繰り出している。
これは、ほんまにすごいことで、新古今和歌集に収録されている他の歌人が、くだらないかと言われたら、全然そんなことない。
藤原俊成、藤原定家、後鳥羽上皇はもちろん、万葉集以降の優れた和歌も収録されているんや。
その中にあって、一人だけ異彩を放つ存在感を示すっていうのは、本物の天才じゃないと不可能や。
現代の何かに無理矢理置きかえるなら、将棋の藤井聡太みたいなもんや。
まわりのプロが絶対に思いつかないような「ええ?」という手を指しても、実はそれが勝負を決める手だったりする。
藤井聡太にしか見えてない世界というのがそこにはある。
和歌に関しても、西行にしか見えてない世界があって、西行からしたら、
「ああ、みんなこういう詠み方はできへんのやなあ……」
って、ずっと思ってたような感じがするんや――
しばしの沈黙の後、颯一郎が口を開いた。
「じゃあ、そういうすごい歌の詠み方を、みんなに教えてあげたりはしなかったの?」
「そりゃあ、無理や。藤井聡太が、『こういう時は、こういう風に指すんやで』って教えてくれたとして、みんながそういう風にできるんやったら、世の中藤井聡太だらけになるやんけ。それと一緒や」
「ああ、そうか・・・・・・」
「ポイントは二つや。ひとつ『西行は仏教の修業をするつもりで出家したわけじゃなかった』。ふたつ『西行の和歌の才能は、抜きん出ていた』」
「だから、仕事をやめたんですか?」
「そこや・・・・・・」
黒縁は、メガネをクイッと持ち上げ、小さく笑った。
「西行は、『自分の本心』に、向き合い、それに従うことを選んだんや。そして、『自分の本心』に従って生きることを選ぶことが、自分を最も幸福にすると直感していたんやと思う。それがたとえ、世間に背くことになったとしても。そして、出家した後も、西行は歌を詠むことを通して、自分の心と向き合い続けた人だったんよ」
しばしの静寂が、教室に訪れた。黒縁はそれ以上の言葉を発せず、颯一郎も空気に飲まれたかのように、沈黙し続けていた。
(自分の心と、向き合う)
颯一郎の心の中には、その言葉が何度もこだましていた・・・・・・
「心なき」
黒縁が、西行の歌を音読し始めた。
「身にもあはれは知られけり鴫立つ沢の秋の夕暮れ」
「どうや、最初に聞いた時より、なんか違う歌に見えたか?」
「うん、なんとなく、ちがう感じがします」
「それでええねん。それで」
黒縁は、満足げに椅子の背もたれに深く身をあずけた。
「師匠。でも、もう9時過ぎました」
「え? まじか! 帰らんといかん。すまんな、話が長くなってしもうた」
帰り道、自転車を漕ぐ颯一郎は、夜風を感じながら繰り返しつぶやいていた。
「自分の心・・・・・・自分の心・・・・・・」
自分の心と向き合う・・・・・・。
そして、自分の本心に従って生きる・・・・・・。
そんなことを考えたこともなかったし、とても大切なことのような気がするけど、
一体何をどうすればいいのか、颯一郎にとってはすごく難しいことのように思えた。
(つづく)