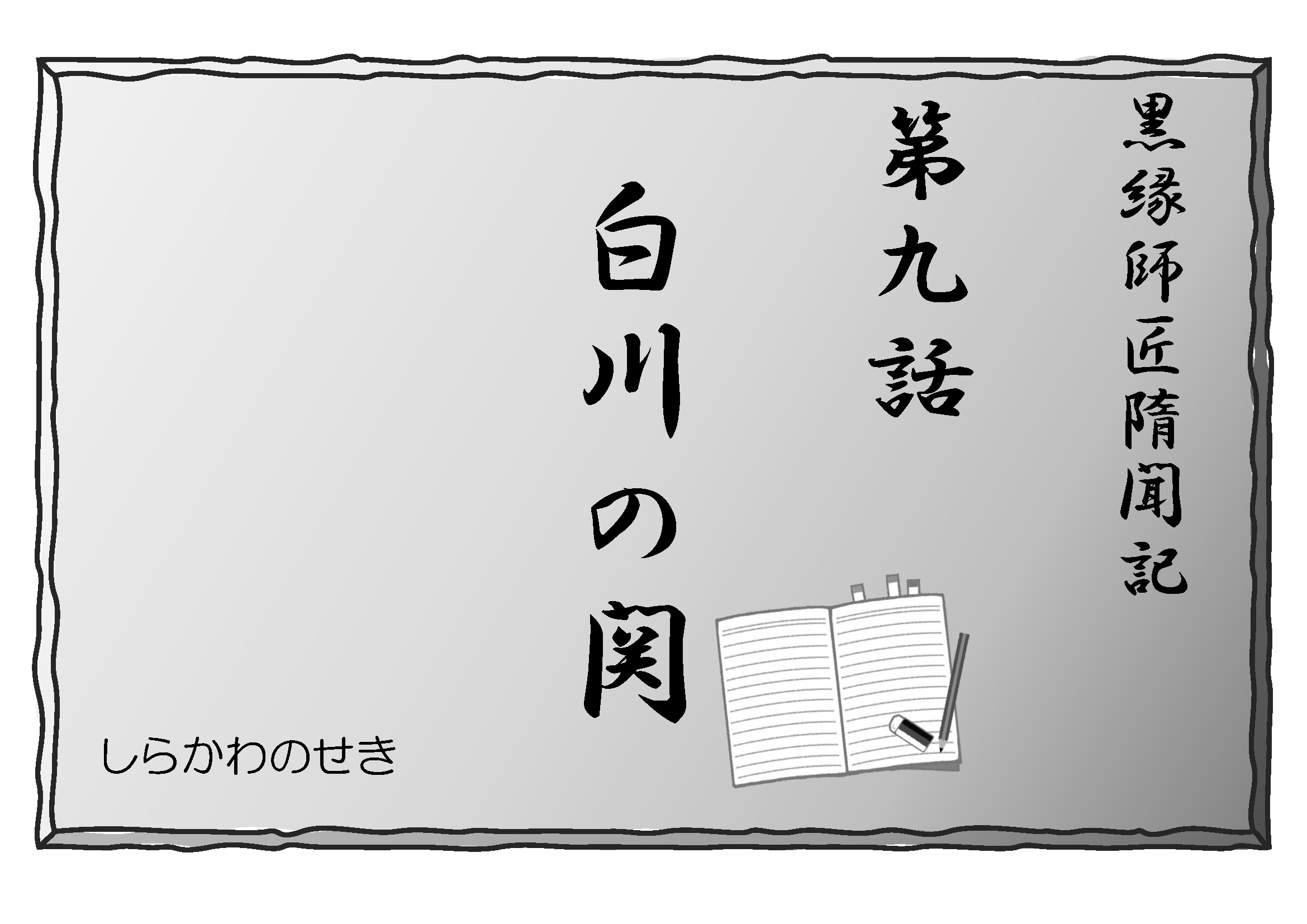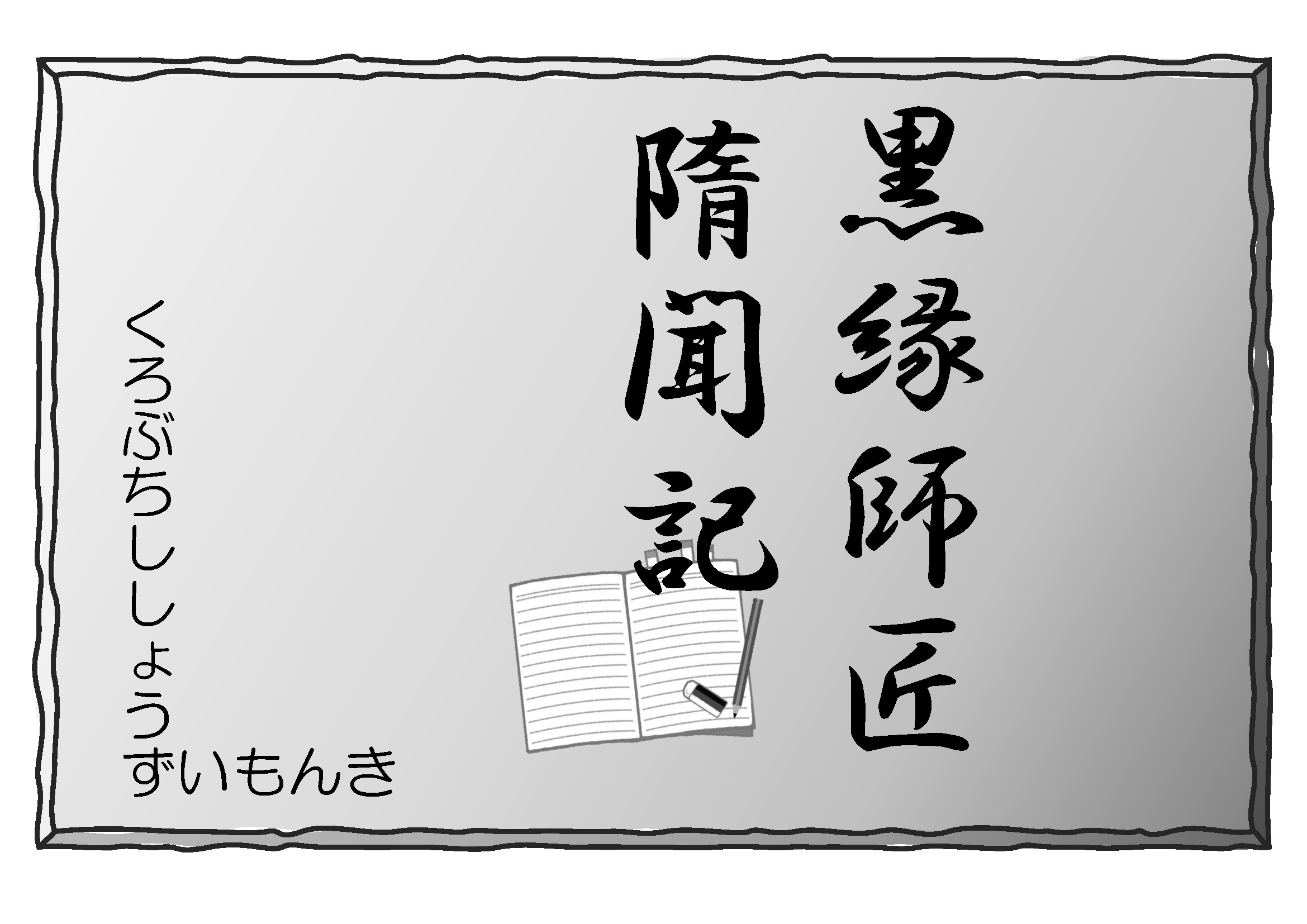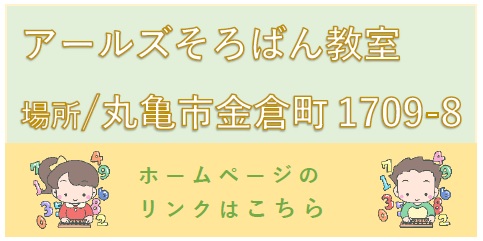夏休みも残り1週間となった。
2学期が始まれば、早速颯一郎たち3年生には2回目の「入試型5教科テスト」が行われる。
黒縁が、珍しく「5教科テスト」の過去問題を手にして、
「やってみろ」
と颯一郎に渡してきた。
普段、黒縁がこうした過去問題のプリントを生徒に渡すことはほとんどない。
「そういうのがほしい子は、ビシバシ塾行ったらええねん」
が黒縁の口癖だ。
綾子の方は、この黒縁塾での最後の課題として、植木算に取り組んでいる。
「両端に木があると『間の数+1』でしょ、両端に木がないときは『間の数-1』でしょ、かんたんかんたん」
などと言いながら、問題をすっかり解き終えた綾子をじっと見ていた黒縁は、
「じゃあ、確認テストね」
と1枚のプリントを出した。
プリントはA4サイズで、問題は1問しかない。
綾子がこれまで解いてきた問題の中から、黒縁が選んだ問題だった。
72mの道のはしからはしまで、8mおきに桜の木を植え、さらに桜の木の間に2mおきにくいを打ちます。桜の木とくいはそれぞれ何本必要ですか。
「これだけ?」
綾子は拍子抜けしたように黒縁に聞く。
「そうだよ。やってみて」
黒縁が静かに告げて、すぐにパソコンモニターに視線を移す。
綾子は自分の席に戻ってさっそく解き始める。
「72÷8=9 はしからはしまでだから、9+1=10 『桜の木 10本』、えっと次・・・・・・えっと、えっと、10÷2=5だっけ・・・・・・」
すでに何回か解いたタイプの問題のはずなのに、やや苦戦しているようだ。
そんな綾子をチラッと見た黒縁が、
「綾子どの、前にいらっしゃい」
と黒縁の机の前に綾子を呼ぶ。
4人掛けのダイニングテーブルが「教師机」として使われているのだが、奥に黒縁が座り、対面する形で生徒が座る。
黒縁は、解説に黒板は使わず、もっぱらこの机の上で生徒に勉強を教えていた。
「書いたところまで見せて」
と綾子からプリントを受け取った。
プリントに綾子が書いた式
72÷8=9
9+1=10
10÷2=5
を見て、黒縁がたずねる
「10÷2って何?」
「えっと・・・・・・そこはわり算かなと思って」
それを聞いた黒縁は、右手に持った赤ペンで激しくペン回しを始めた。
「解き方を丸暗記するからそうなるんや。今までの算数の勉強もどうせそうやってきたんやろ」
少し強めの口調で黒縁に言われた綾子は、ややむくれた感じになって、
「でも、それで100点とれちゃうもん」
と言い訳する。
「お前さん、どっち向いて勉強してんだよ」
呼び方が、「綾子どの」から「お前さん」に変わる。
これは黒縁が説教モードに入った証拠だ。
「計算の意味、数字が表すもの、そういうのを理解して、問題の構造を把握するために練習するんや。意味も考えずに、手順を丸暗記して、100点取れたらオッケーみたいな勉強で、いつまでも通用すると思うな。中学高校の数学でつまずいて落ちこぼれたくなかったら、その甘ったれた考え叩き直せや」
黒縁にまくし立てられて、綾子の目が少し赤くなった。
そして、やや悔しそうである。
そんな表情を一瞥するも、無視して黒縁が続ける。
「この 10÷2 の10ってなんや?」
「え、桜の木です」
「10本の桜の木を2つに分けてどないすんねん。8÷2やろ、ほら、もう1枚、数字を変えただけの同じ問題や、やり直してこい」
黒縁は新しいプリントを綾子の目の前に出す。
すでに用意していたのだ。
まるで、こうなることが分かっていたかのように。
その後、綾子はこの『桜の木とくい』のプリントを7枚やってやっと合格になった。
黒縁が指摘する通り、綾子はこれまで、生来の記憶力にまかせて、算数の解き方は「丸暗記」して乗り切ってきた。
しかし、そこを黒縁にぶった切りにされたのである。
「勉強ができるつもりでここまで来たんやろが、そのままやとお先真っ暗やぞ。ちゃんと数字の意味、問題の意味を考えろ。これは宿題や、解かなくていい、問題に合うように図を描いてこい」
数枚のプリントを渡されて、その日は終わりになった。
帰り道、颯一郎の前を歩く綾子は、ずっと下を向いている。
すれ違う人が、俯きながら歩く女の子をよけるとき、ちら見する様子を見て、
「もしかして、泣いてるのか?」
と颯一郎は思った。たしかに、今日の綾子への容赦ない言葉の数々は、「ちょっと言い過ぎじゃなかろうか?」と教室の端で聞いていた颯一郎も思った。しかし、それでも泣くほどのことでもないだろう。
颯一郎は、後ろから綾子の肩をちょんと小突いて、
「コンビニ、寄る?」
と声をかけてみた。
綾子は下を向いたまま、こくりと首を動かし、
「オレンジ・・・・・・」
と小さくつぶやく。つまり、颯一郎に買ってこいという意味なのだろう。
オレンジジュースを2本買って、颯一郎がコンビニの外に出ると、綾子は駐車場の端っこにあるコンクリートブロックにちょこんと座っていた。
隣に座った颯一郎が、綾子にジュースを手渡した途端、突然綾子が声を上げて泣き出した。
「あああああああああ″あ″あ″あ″」
「ちょ、綾子!」
颯一郎が、あわてふためいて、あたりを見回す。これじゃまるで、自分が綾子を泣かせてるみたいじゃないか。
「落ち着け綾子。落ち着けったら」
「ひっく……れない・・・・・・」
しゃくり上げながら、綾子が何かを言っている。
「このままだ・・・・・・なれないよ!ううううう……」
おえつで声をつまらせながらひとしきり泣いて、颯一郎はうろたえて、そして少し落ち着いた綾子が、ポケットタオルで涙と鼻水をふきながら語り出す。
「だれにも内緒なんだけどね。なりたいものがあるの」
「そうなんだ」
「何になりたいのか、聞かないのね? 普通聞くとこだよね! なんで?」
「いや、なんで? 聞かれたくないかもしれないと思って」
なんか、颯兄ぃっていつもそうだなと思う。いつも、颯兄ぃの方からは聞いてくれない。
だから、こっちから話をがんばってしてる……
「ぜったい獣医になりたいの。だから、めちゃくちゃ勉強できないとダメなの」
「ああ、獣医さんか。犬とか好きなの?」
たくさんの犬や猫にかこまれている綾子の姿が、颯一郎の頭に浮かぶ。
「ちがうよ、イルカだよ。水族館で、イルカや他のお魚のお世話をするの」
「え? 水族館? あれって獣医さんなんだ」
「獣医さんじゃなくても水族館で働くことはできるけど、綾子は獣医さんになって水族館で働きたいの! でも、このままだと無理だって、ししょ~が言う・・・・・・」
「獣医になれないとは言われてないでしょ?」
「でも、お先真っ暗とか、勉強してるつもりとか、中学で落ちこぼれるとか、言われたもん」
「ああ……」
たしかに、今日の師匠は言い過ぎだろうと颯一郎も思った。
でも、よく考えたら、自分もあれくらいは言われているかもしれない。
もしかして、自分はにぶいのだろうか。
「でも、宿題出たんでしょ? 師匠が宿題出すってことは、見捨てていないからだと思うよ」
「そうなの?」
「だって、うちの師匠、普段は宿題出すような人じゃないし。『家で何したらいいですか?』って聞いても、『やることないなら、アニメでも見たら?』とか言っちゃう人だし」
颯一郎と話をしているうちに、綾子もだいぶ落ち着いてきたようだ。
「そっか、ししょ~ってやっぱり変わってるね」
ジュースを飲みほした颯一郎が立ち上がって言った。
「なれるといいね」
「ええ? 綾子、これでも今の塾に慣れたと思ってるけど」
「ちがう」
「え?」
「獣医にだよ。なれるといいね」
颯一郎の言葉を受けて、綾子もすっと立ち上がった。
「うん! ありがとう!」
ふっきれたような笑顔だった。
翌日の綾子はうるさかった。
「ししょ~! 分かったよ! 式の意味、分かったよ!!!」
教室に入るなり、色鉛筆で図を描いたプリントを手に、黒縁の前に突進してきた。
「こら、他の子もいるんだから、少し音量下げて」
「あ、はい。すいません。でも描いたら分かったんです」
「どれどれ?」
綾子から手渡されたプリントを、黒縁はしげしげと見つめた。昨日渡した3枚のプリントは、『桜・くい問題』と黒縁が呼んでいる植木算の文章題が1問ずつ出題されていた。
綾子が描いてきたのは図というより絵だ。何十本も描かれている桜の木は、その1本1本が茶色と桃色で描かれており、木と木の間には、黒色の「くい」が刺さっている。地面を表す長い横線のところどころには、緑色の草が生えていて、桜の木の上には、小鳥が数羽飛んでいた。
しかし、あいだの長さや、全体の長さなどの数値もしっかり書かれており、算数的な要素にも抜け目がなかった。
(この図が描けるなら、心配ないな)
黒縁はそう思いながら、書き込まれた数値に間違いがないか、問題と照らし合わせていると。
「ししょ~。なんで笑ってるの? どっか間違った?」
と綾子が心配する。たしかに、この時の黒縁は微笑していたのかもしれないが、それは綾子の描いて来た図が黒縁の好みだったからだ。
「え? ああ、いや楽し気な図だなと思って。間違ってはないよ。綾子どの、よくやった。えらい」
「やった!」
黒縁に褒められて、綾子は素直に喜ぶ。
「さて、綾子どのがこの教室に来るのも、今日が最後なので、最後の勉強をしようか」
そうだった。桜の木の絵を描くので頭がいっぱいになっていて、綾子はすっかりそのことを忘れていた。
分かっていても、なんだかいやだなあと、気持ちが傾いていく。一点の曇りもない澄んだ満月の光を、雲が隠すように。
「諸行は無常なり、とりあえず今日を精一杯や。さあいくで、理科の勉強や」
黒縁はパソコン画面に1つの俳句を打ち始めた。
菜の花や 月は東に 日は西に
「え? これが理科?」
綾子がキツネにつままれたような顔をする。
「そうや。この俳句に見えている月をここに描いてみて」
と黒縁は白い紙を綾子の前に差し出した。
「え……月? 月を描けばいいの?」
うなずく黒縁を見て、綾子は差し出された紙に鉛筆で月の形を描くのだが、その形は・・・・・・半月だった。
「これでいいの?」
黒縁がわざわざ念を押してきたので、綾子はいやな予感がしたが、
「うん、これでいい」
と押し切った。
「まあ、月の満ち欠けを習うのは、普通は6年生だからね。間違っても気にしなくていいけど」
「え、だって。月だよ?」
「そうだよ、月だよ。月って形変わるけど、なんでか分かってる?」
言いながら、黒縁は理科の資料集を本棚から取り出して説明を始めた。
一通り説明を聞いた綾子は、
「へえええ。知らなかった。夕方に東の空に見える月は、満月なんだね」
と感心しきりである。
「しくみが分かったなら、次は正解できるかな?」
言いながら、黒縁がまたパソコン画面に打ち込んだ和歌がこれだった。
東 の 野にかぎろひの 立つ見えて かへり見すれば 月かたぶきぬ
「さあ、月の形を描いてみて」
表示された和歌を音読した後に黒縁が指示するも
「ええ? 意味わかんないんですけど」
と綾子は不満顔である。
まあ、無理もないかと黒縁は思い直し、少し説明する―――
「かぎろひ」というのは、明け方の光や。
日の出の時刻に、東の空が赤く染まる様子。
「ああ、もうすぐお日様が上って来るな」と思ったとき、西の空を振り返って見ると、月が沈もうとしている。
そういう情景を詠んだ歌だよ。
もっと深読みする解釈もあるけど、今はこれでいい―――
「じゃあ、さっきの菜の花のやつとは逆なの?」
綾子は、黒縁に示された和歌をじっと見つめて視線をそらさないでいる。
こういうとき、何か正解を求めて指導者の顔色をうかがう小学生が多いのだが、今の綾子は自分で何かを考えようとしていると黒縁は判断した。
「その通り。夕方と、明け方の違いがある」
「ええ? でも、やっぱり月の形なんて分からないよ」
あきらめようとする綾子を黒縁がたしなめる。
「さっきの、月と太陽と地球の関係から考えて。『この形じゃないか』と判断をすることが大切なんや。考えることをやめたら、勉強にならん」
「はぁい・・・・・・」
綾子は、さきほど黒縁が持ってきた理科の資料集とにらめっこしながら、数分の間考えた後、
「もしかして、満月?」
とつぶやいた。
「綾子どの、合格や」
黒縁が綾子の顔の前で親指を立てると、綾子は
「やった!」
と喜んだ。
「でも、なんかこの和歌、学校で習ったことあるかも……」
綾子が首をかしげる。
「ほうほう、ふつうは中学校で習うんだけど、いい学校だね。柿本人麻呂という人の和歌だよ。なんと、今から約1300年前の人」
「ええええええ? そんな昔なの?」
「そやね。万葉集という日本最古の和歌集があるけど、その中でもこの柿本人麻呂は別格。あと一人、山部赤人という人がいて、この2人はその後『歌聖』と呼ばれるようになった」
「火星? 宇宙人?」
「そうやない。和歌のすごい人」
「ぜんぜんわかんない。だって、朝に太陽が出てきそうで、月がかたむいているよってだけじゃん。そんな歌、だれでもよめそう」
「まあ、そうだね」
「すごいと思わないけど……」
―――わしは、柿本人麻呂のすごさは理屈じゃないと思ってるんやけど、あえて言うなら、「同じ情景で同じ題材を詠んでみて柿本人麻呂のように言葉を紡げるだろうか」とよく思う。
たとえば、これはあくまで想像だけれども、この和歌を詠んだ時の人麻呂と同じ景色をわしが見たとして、どうなるだろうか。たぶん・・・・・・
かぎろひに ふりさけ見れば 西の山 かたぶきかける 月をほにゃらら…
みたいな腰抜け短歌になってしまうと思う。
柿本人麻呂はいろいろとすごい歌人だけど、まず「の」の使い方が上手い。
「の」をかぶせて歌のリズムを作っているんや。
「東(ひんがし)の」「野に」「かぎろひの」
ここでの、たたみかけるような「の」の使い方は素晴らしいの一言で、他にも有名なのが
あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の 長々し夜を ひとりかも寝む
上の句で「の」「の」「の」「の」とリズミカルに引き付けて、下の句でドカンと言いたいことを言う。
しかも、下の句に「の」が一つもない所は、最初の
「東の」「野に」「かぎろひの」
とよく似てる。
たぶん、こういう調べの作り方は得意だったんやろね。
この和歌にしても、言ってることは単純極まりなくて
「ひとりで寝るのはさびしいな」
としか言ってない。
なのに、1000年以上の時を経て、優れた和歌として残っているということは、歌の内容と調べの調和が誰も真似のできない境地に達しているからだと思う。
これは柿本人麻呂に限らないことなんやけど、万葉時代の和歌の魅力的なところは、その歌のほとんどが「生活歌」だからだと思う。
地に足がついているんやね。
すべてが単純な歌ばかりではない。
たとえば、さっきの「東の野に」の歌も、そのとき一緒にいた軽皇子 を次世代を担う太陽にたとえ、「かたぶく月」は死んでしまった軽皇子の父親にたとえているという背景がある。
ダブルミーニングや。
しかし、その背景を知らなかったとしても、単なる叙景歌としても感動を呼ぶ力が「東の野に」はある。
何が言いたいかと言うと、万葉集には、見て感動した景色、思ったこと、感じたことをこねくり回さずに直線的に詠んでいるものが多い。
わしの好きな和歌をちょっと紹介するで。
淡路の 野島の先の 浜風に 妹が結びし 紐吹きかへす
巻向 の 檜原 もいまだ 雲ゐねば 小松がうれゆ 淡雪 流る
淡海 の海 夕波千鳥 汝 が鳴けば 心もしのに いにしへ思ほゆ
若の浦に 潮満ち来れば 潟 をなみ 葦辺 をさして 鶴 鳴き渡る
あすよりは 若菜つまむと しめし野に 昨日もけふも 雪はふりつつ
田子 の浦ゆ 打ち出 でて見れば 真白にぞ 富士の髙嶺 に 雪は降りける
国国 の 防人つどひ 船乗りて 別るを見れば いともすべ無し
わが妻は いたく恋ひらし 飲む水に 影さへ見えて 世に忘られず
父母 が 頭掻 き撫 で 幸 くあれて 言いし言葉ぜ 忘れかねつる
信濃なる 千曲 の川の さざれ石も 君し踏みてば 玉と拾はむ
―――
「万葉集には、天皇から庶民までの約4500首の歌が収録されている。今日の話を聞いて、もし興味がわいたら、自分でいろいろ調べてみるといい。わしら現代の日本人と、1000年以上前の日本人。生活や仕事のやり方はすっかり変わってしまったけど、思うことや感じることってあまり変わらないんやな、とわしはよく思うんやねぇ。あ、ちょい綾子どのには、退屈やったかな。最後の日なのにごめんやで」
黒縁が頭を搔いていると、
「………ししょー、ありがとうございました」
綾子はぺこりと頭を下げた。
(なんか雰囲気変わった……?)
と黒縁は感じたが、その感情を深追いするのはやめにした。
この子とは、今日でお別れ、もう一生会うこともないかもしれない。
別れ際に、しんみりするのは、黒縁の好みではない。
さあ、では今日も仕舞いにするかと黒縁が立ちあがった時、
「し、ししょおおおおおおおおお! おかしいです!」
突然、颯一郎が叫び声を上げた。
「うるさいわい、颯一郎。何がおかしいねん」
うっとうしそうに手を振る黒縁のところへ、颯一郎が「5教科テスト」の過去問を手にして突っ込んできた。
「合計100点超えました!!」
颯一郎の目が、輝いている。まるで、銀河大戦に勝利したような喜びようである。
「………」
ところが、黒縁は、黙ったままiPadやUSBメモリをかばんに片付け始めている。
いつもの帰り支度である。
「あれ? し、師匠! すごくないですか?」
「ああ……そか、よかったな」
黒縁の反応が、あまりにもそっけない。
「ひどいです。おれ初めて合計100点超えたんですよ? すごくないですか?」
「今日は秋刀魚や……」
「ししょ~~~~!!」
「おい颯一郎」
やっと黒縁が颯一郎と目を合わせる。
「5教科テストの『あるある』、知ってるか?」
「え、『あるある』? 聞いたことないし」
「上がると、その後、下がるんや。ということは、次の5教科テストでは、点数が下がるんちゃうか?」
「ひっ! そんなん知らんし!」
黒縁と颯一郎がやり合っていると、すでに靴を履いてドアの前で待っていた綾子が待ちきれない様子で声を出す。
「おなかすいたよ~。帰ろうよ~」
「ちょっ、綾子、待って……師匠、それほんまですか?」
「ああ、だいたいそうなる。特に急に上がった奴ほど、次でドーンと下げるんや。そういうもんや。そうやな。3回連続で100点超えたら、ほめたるわ。過去問は、用意したる」
「ふへぇぇぇぇ」
力が抜けたように、颯一郎は肩を落とした。
「油断するなということや。1回やそこらまぐれ当たりしたくらいで調子に乗るな」
教室を閉めて、階段を下りきったところで、あらためて綾子が黒縁にお辞儀をした。
「ししょ~。また来ます」
「え、また来るの?」
「だめですか?」
「いや、だめじゃないよ。来る・来ないは綾子どのの自由。だが無理はしたらあかんで」
「分かりました」
綾子と颯一郎が帰って行く。
帰って行く生徒の背中を見送るなんてことは、めったにやらないのだが、この日の黒縁は2人の背中をしばらく見つめていた。
(つづく)