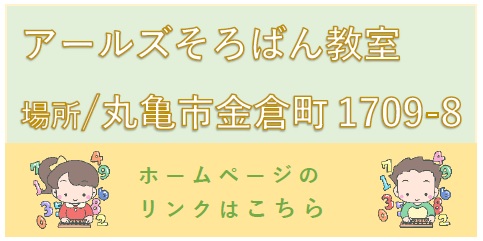先日の「先生にききたいこと」の紙にたくさんの質問をいただいております。
その中には、保護者の方からの質問もいくつかあり、大変嬉しく思っております。
これらの質問は順を追ってお答えしていきますが、今日はその第一弾となります。
小学校入学前の家庭での数の学習について、ぜひ先生にご意見をお聞きしたく、私も書きました。
小学校1年生では「さくらんぼ算」や「10の合成・分解」といった数の感覚を育てる学習がはじまると聞きました。そこで、年中・年長のうちに家庭でどのような遊びや声かけ、取り組みをしておくと、入学後にスムーズに理解できるのかを知りたいです。
また、そろばんを通して、こうした数の概念(さくらんぼ算や10のまとまり)に対するつまずきが少なくなるということはあるでしょうか?もし、そろばんで身につきやすくなる力や、逆に気をつけておくとよい点などがあれば、あわせて教えていただきますと嬉しいです。
ご丁寧な文章でのご質問をいただき、大変恐縮しております。
私もなるべく丁寧にお答えしようと思います。
もくじ
小学校に向けての備え
カレーを作る能力
1つ目の質問は、小学校入学後の学習に備えての、家庭での取り組みについてです。
まず、前提として、小学校の学習過程は、世の中で言うと時代遅れの最後尾なので、強く意識する必要はありません。
しかし、子供の数の感覚を鍛えることは大切です。
このことについて、今は亡き私の師匠は「カレーを作る能力」とよく言っていました。
カレーをひとつの具体例と考えるなら、料理すること、そのお手伝いをすることは数の感覚を育てるのにとてもよい体験になるでしょう。
材料の数量を数えることに始まり、重さ、体積、割合など、算数で学習することの多くの要素が料理には含まれています。
こういうことを、リアルな実感として体験できることは、子供にとって大きな学習の機会になります。
無理のない範囲でお母さんのお手伝いができるといいですね。
ワークブックより生活
こうした、「就学前の数の学習」でよくみられるのが、書店でワークブックを買ってきて子供にやらせる保護者の方です。
「苦手克服のため……」というのでなければ、悪くはないのですが、私が同じ立場ならその方法はとらないでしょう。(これについては後述します)
生活の中には、数に関係する場面がいくつもあります。
「今日は何月何日」
「キャンプの日まであと何日」
「今は何時何分」
「食器棚の下から二番目」
「お買い物でトマトを3つ」
「冷蔵庫から卵を4つ取って」
などなどです。
こうした、生活の中での数の意識を明確化・言語化することで、机上の紙だけで学習することでは得られない、実体験に基づく数の実感や感覚が育つことになります。
これは、ワークブックの学習では得られないことです。
遊びで育てる算数の力
また、実生活やお手伝いだけでなく、遊びとして算数の力を鍛えることはいくらでも可能です。
電子的なおもちゃではなく、アナログなおもちゃの中には、算数の力、数の感覚を育てるものがいくらでもあります。
「オセロ」「どうぶつしょうぎ」「豆つまみ」「知恵の輪」「折り紙」「あやとり」「すごろく」……などなどですが、
私が列挙するまでもなく、保護者の皆様の頭に浮かぶ「これいいかも」と思う遊びがあれば、
いろいろやってみて子供が一番楽しんでくれる遊びをご家庭でされるのが良いと思います。
このように、数の感覚を育てることは、ワークブックや教材に頼ることなく、どんな家庭でも行うことができます。
ぜひ親子で楽しんでください。
そろばんと算数・そろばん学習上の注意点
ふたつ目の質問は、そろばん学習と算数の関連、そろばん学習における注意点についてでした。
そろばんと算数(スポーツにたとえると)
ここで、スポーツの話をいたします。
どんなスポーツにも共通することは、競技者の基本的な身体能力が高ければ高いほど、上達しやすいことです。
たとえば、走力ひとつとってみても、足が速いというのは多くのスポーツにおいて強力な武器となります。
そろばん学習は、スポーツにおける基礎体力を鍛えるものだとお考えください。
しかも、常人離れした力が身につきます。
よって、その基礎力をもってすれば、学校で学習する程度の算数・数学で困ることはほぼありません。
つまり、つまづきはほとんど心配する必要はありません。
考えられる注意点
ただし、注意点はあります。
それは学校の算数が簡単すぎて苦痛を感じることがあることです。
たとえば、途中式など書かなくても見た瞬間に答えが分かるのに、途中式を省略することが許されないようなことがあります。
「なんでこんなこと書かないといけないの?」
と子供が不満や疑問を持つことになる場合がありますので、そこはうまくフォローしてあげてください。
算数の文章題が苦手な場合
算数でつまづく可能性があるとすれば、文章題です。
上で「ほとんど大丈夫」と書いたものの、今回、他の保護者の方からもいただいている質問があり、それは
「計算はできるけど文章題が苦手」
というものでした。
これは
①実体験の豊富さ
②国語力
が問題になってきます。
実体験と算数の文章題
まず実体験のお話からいたします。
保護者の方からすれば
「せっかくそろばんを習っているのに、算数の文章題ができないなんて」
と残念に感じられることでしょう。
そうなったときに、
「文章題のワークブックを買ってやらせよう」
という方がいますが、この方法は賛同しかねます。
「文章題が苦手だから、文章題のワークブックをやらせる」
これについて私が歯に衣着せず、太く赤くして言うなら、虐待です。
ピーマンを食べられない子供の口に、ピーマンを押し込むことを想像してみてください。
その子供は、ピーマンをますます嫌いになるのではないでしょうか。
同時に、自分を守ってくれるはずの親という存在にピーマンを強要されたという心の傷を負うことにもなります。
ということで、私は「ワークブックによる苦手克服」は、手法として好みません。
では、文章題が苦手にならないためには、どうすればよいか。
これも、ひとつ目の質問への回答にあったように、
「生活のさまざまな場面で数を体験し、言語化する」
ことを日常に落とし込んでいるかどうかが大きな鍵を握ることになります。
文章題というのは、
「数の操作が言語化されたもの」
なので、
「数の操作を言語化する(例:料理の手伝いをする。お買い物の代金やおつりを考える)」
こうした体験が豊富であればあるほど、その体験を応用して思考することで文章題に対応できる子供になります。
最近の子供は、こうした体験が希薄になっているのではないかと感じることが多くなってきました。
つまり、紙ベースでの、実感を伴わない学習ばかりやっているのではないかという想像です。
そのためか、文章題をパターン認識して、式を丸暗記する子供をよく見かけます。
とても応用力があるとは思えません。
これは、学力が相当高いと思われるような生徒でも見受けられる現象です。
ですから、学校のテストの成績が良いからといって安心していては、足下を掬われる場合もあります。
特に昨今では、学校のテストの過去問も出回っていますので、それを使用してテスト勉強をすれば、本質を理解していなくてもよい点数が取れてしまいます。
そんな子供を育てたくて、子供に勉強に励んでほしいとは、普通は思いません。
しかし、現実にはワークブック学習、過去問テスト勉強が世の中にあふれていて、それに疑問を感じることもなく普通のことと受け止めている保護者が大半です。
「おかしい」「ちょっと変だぞ」
と思ってくれる方が増えることを願っています。
数を日常に落とし込めているかいないかは、簡単な質問をいくつかすることで大体分かります。
「今日は何年何月何日何曜日」
「自分や家族の生年月日(和暦・西暦)、年齢」
「身長(㎝・m)体重(g・㎏)」
「自分の家の住所」
「親の携帯番号」
「ペットボトルや紙パックの容量(mL・㏄・L)」
などです。
算数の文章題をどうにかする前に、こういう簡単なところから、始めてみてください。
何事も、こつこつやっていかなくてはなりません。
国語力と算数の文章題
さて、算数の文章題ができない2つ目は、国語力でした。
国語力は、家庭とアールズの両方で育てましょう。
できるだけ曜日を増やし、時間を延ばして、教室での国語学習の時間を確保できるとよいと思います。
では、家庭ではどんな取り組みができるでしょうか。
これについては、他の方からの質問もありますので、次回の記事にまわしたいと思います。
次回の記事も、皆様のお役に立つ内容になるよう、一生懸命書かせていただきます。
今回は以上です、最後まで お読みいただきありがとうございました。
「その2」はこちらです