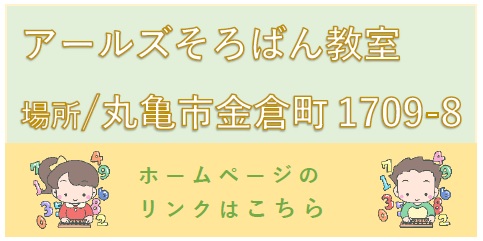さて、前回記事で保護者の方からの質問にお答えしました。
今回は、追加の質問をご紹介しつつ、
前回の記事からつながる算数の文章題についてのご質問にお答えしようと思います。
学校の成績で、国語・算数ともに文章問題が努力を要するという評価で、親としては予想通りといった感じなのですが、とにかく読書が苦手です。
国語の勉強の割合をふやした方が良いでしょうか。
暗算をがんばってどんどんできるようになってびっくりしていますが、学校の勉強とうまく結びついていないようです。もう少し見守っていた方が良いでしょうか。
前回記事では、算数の文章題の解決法として、「実体験」と「国語力」の2つにアプローチすることに触れました。
ここでは、国語力をどうするかについてご説明いたします。
国語力を育てるには、アールズで国語をがんばるのは有力な方法です。
全力で通ってもすべての国語学習を修めるのに何年もかかります。
家庭でできる国語力育成
さて、家庭でできることを考えます。
ひと口で言うと、「習慣化」に尽きます。
習慣化の意識を「会話」と「読書」の2つに向けてください。
「会話」の習慣化
日常会話の意識を変えることで、国語力を育てましょう。
これまでの会話のやりとりでは言語化せずに流していたことも、意識して言語化するようにします。
特に、「理由」について言語化する意識を高めることをおすすめします。
何も難しく考える必要はありません。
「桃とすいかどっちが好き?」
という質問に答えたときの「なぜ」を言葉にしてみるのです。
素朴な「なぜ」を掘っているうちに、思ってもみない発見をすることもあります。
「読書」の習慣化
読書の習慣はあまり難しく考える必要はありません。
本である必要もありません。マンガでもかまいません。
・本をよく読む子供の家庭環境
これはそもそも論なのですが、読書習慣のある家の特徴は次の二つです。
① 家に本が大量にある(数百冊~千冊以上)
② 親が本をよく読む
身も蓋もない話ですがこの通りです。
しかし、このような環境は一朝一夕に作れるものではありませんので、これから読書習慣をどうにかして家に導入したい場合を考えてみましょう。
・読書習慣がない場合どうするか
まず、現在読書の習慣がない人は、毎日本にさわることから始めてみてください。
何事も、スモールステップから始めるのがよいと思います。
さわることができたら、次はめくってみましょう。
めくるだけです。
読まなくていいです。
挿し絵をながめるだけでも大丈夫です。
とにかく、本という物体に慣れ親しみましょう。
時間を決めたり、ルーティン化するのは上級者向けコースです。
今、本を読む習慣が子供にない場合、まずは家族で一緒に
「本をさわる、めくる、ながめる」
をやりましょう。
そして感想を言い合うのです。
「かわいい表紙だね」
「100ページもあるよ」
「紙がかたいね」
のように、本の内容と関係ない話でもいいのです。
さて、こんなことを始めの一歩として、だんだん本に触れる時間を増やしてください。
任意のページを数行読む。
任意のページを読み聞かせる。
など、ここからは皆様が思いつくアイデアで進めていってください。
・ふつうにしていると本が嫌いになる
これは何をやっているのかというと、心理的な壁の除去です。
本が苦手な子供は
「本は押し付けられるもの」
「読んでもつまらないもの」
「読書は義務」
と思っています。
学校からも読書の押しつけをされるので、子供はますます本が嫌いになってしまいます。
今の子供は、まさに本が嫌いになってもしょうがないような環境におかれています。
こうした読書に対するネガティブな感情を薄めることを、習慣化の第一歩にすることをおすすめします。
・自信を取り戻す言霊「今は、まだ」
親としては、子供が本を一冊を読み切る姿を見たいと思うでしょうが、あせる必要はまったくありません。
ここで、便利な言葉を紹介します。
「今は、まだ」
です。
「今は、まだ一冊を読み切ることをしていないけれども、必ず読めるようになる日が来る」
と考える、または言葉にします。
こうすることで、現状できていないのは、できるようになる過程の一つに過ぎないと受け止めることができます。
これは、勉強やスポーツをはじめとする、あらゆる目標達成や願望実現に応用可能です。
・好きな分野に特化する
もう一点、読書習慣につねげるヒントは「本人が好きなもの」を与えることです。
プリキュアやポケモンでもいいし、宇宙や恐竜でもいいでしょう。
昔の生徒に、「ダムが好き」という子がいました。
読書を「書かれている文字を読む行為」とするならば、図鑑やマンガやムック本や雑誌も立派な読書です。
「物語の本」にこだわる必要はないと思います。
「ページをめくる」という動作の繰り返しが大事です。
その動作が、誰も見ていない場所で、子供一人でするようになれば、読書習慣はもはや手に入れたも同然です。
子供は、親が見てないところで伸びるものです。
親が見ていないところで何をするかの仕組みづくりを、工夫してみてください。
このとき、「強要する」「禁止する」「圧をかける」という要素を極小まで省くことができれば、上々です。
あとは、教室での国語学習との相乗効果を信じて子供を見守ってあげてください。
国語力を向上させる詳しい仕組みについては、近日中に図解入りで別記事にまとめますので、そちらを参考にしてください。
・「今は、まだ読書しなくていい」の可能性もある
とりあえず、ここまで書いてみて思うのですが、読書の習慣がどうしても身に付かない子供は、もしかしたら
「今はまだ」読書をしなくても大丈夫な人なのかもしれません。
人に与えられた才能というのは、さまざまです。
その人ごとの与えられた才能を開花させ、その能力で世の中を生きていくのが人生にとって最も大切なことだとするなら、
「読書」がそこにどのように関わってくるのかは、それこそ神のみぞ知る世界だと思います。
必要な時に、必要な学びが人に訪れると考えたら、今読書習慣がないことを重く考える必要はないのかもしれません。
国語の文章題について
最後に、算数の文章題だけでなく、国語の文章題についてご説明いたします。
「国語の文章題」というのは、
まとまった文章を読んで、その内容について答える問題のことを指していると思われます。
答え方の形式は、「記号を選択する」「抜き出す」「文章中の言葉を使って答える」がほとんどです。
実は、学校で課される、この形式のテストですが、低学年のうちは解けなくても全く問題ありません。
4、5年生くらいになってから、「国語の文章題」ができるようになればいいとお考えください。
低学年のうちは、漢字の読み書きだけ、しっかりやってください。
それ以外は、瑣事です。
文法的なことも、分からなくて大丈夫です。
国語力=テストの点数
ではありません。
私の妻(←さくらぷりんとの漢字担当者)も、無類の読書好きですが、小学生の時は国語のテストでなかなか点が取れなかったそうです。
低学年、つまりシングルエイジのうちにやっておきたいことは、文章問題への対応ではありません。
国語の文章問題をいくら解いても、本質的な国語力は全く上がりません。
身に付くのは「テストでの立ち回り」だけです。
野球で言えば「送りバントの練習」をずっとしているようなものです。
シングルエイジは、別名ゴールデンエイジとも言います。
まさに、黄金時代です。
そんな年齢の子供に、「送りバントの練習」ばかりさせるより、国語力の本質を育てる活動に時間を使いたいのは当然のことです。
しかし、実際には学校のテストでそういうことをやらされ、点数が結果として帰って来るので、それを見た親としては
「これで大丈夫なんだろうか」
とつい不安になってしまいます。
しかし、そういう不安は一種の罠だと思ってください。
不安や心配を起点として、教科書ワークや学習塾に手を出すと、「ひたすら送りバントの練習」が待っています。
結果、学校のテストの点数が向上したとしても「いい送りバントができた」だけのことです。
皆様は、本物の国語力に向かって大切な子供の教育を考えてあげてください。
読書についての補足
最後の最後に補足ですが、「本が好き・嫌い」ということは、私は前世までの魂の遍歴とも関係あると思っています。
前世までは、あまり本に触れてこなかった魂が、今世で「本というもの」を読むのであれば、苦手意識を持つのも無理はないと思います。
または、前世までは日本語以外の言語圏でずっといた人かもしれません。
そういう感覚も頭の隅に置きつつ、導いてあげられるといいなと個人的には思っています。
今回の記事はここまでです。
まだまだ、いくつかご紹介したい質問がありますので、新しいものが書けたらまたお知らせいたします。
最後までお読みいただきありがとうございます。