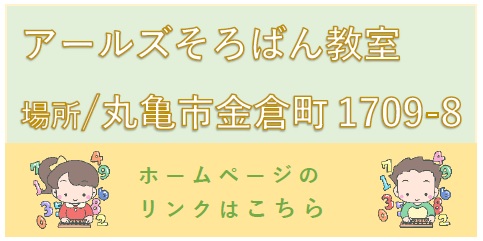教室では、「ことわざ・故事成語・四字熟語」を日常的に学習します。これについて、
「なぜ、ことわざなどを重視するのか、はっきりとした理由が知りたい」
と妻から質問がありました。
保護者の皆様の中にも、疑問に思っていた方がおられると思ったのでこの質問にお答えします。
現代の教育に合ったサイズ感
昔の寺子屋では往来物や場合によっては四書五経を習っていました。
往来物とは、簡単に言えば「手紙のやり取り文例集」のようなものです。
そして四書五経は儒教の教科書です。
時代的にこれらを取り入れるのは違います。
また、分量的にも大きすぎます。
朝から昼過ぎまで、毎日生徒が通ってくれる江戸時代の寺子屋と違って、今の教室は週に数回、合計数時間の学習時間しか確保できません。
その中でそろばん学習を行い、その合間をぬうように国語を学習するとき、たとえば論語を端から端までやるというのはゴールが遠すぎます。
それに対し、「ことわざ・故事成語・四字熟語」は、いわばひと口サイズの切り身のようなものですから、時間の制約がある教室の環境では、大変取り組みやすい学習になります。
人生観と知恵の継承
ほぼ毎日のように、継続的に取り組む音読教材を選ぶとき、その内容には一定の普遍性が求められます。
「ことわざ・故事成語・四字熟語」には、先人たちの経験に基づく人生観や生きる知恵が凝縮されています。
これらを幼い頃から学ぶことで、各々が人生を生きる指針になる可能性も感じています。
私の育った家の台所の壁には、鏡がかかっており、その鏡には徳川家康遺訓が綴られていました。
毎日それを見ながら小学生時代を過ごしたおかげで、徳川家康遺訓を諳んじることができました。
その中でも印象に残っていたのは
「勝つ事ばかり知りて負くること知らざれば、害その身に至る」
という言葉です。
おかげで、勝ち負けのみにこだわらない考え方が身についたのかもしれないと思います。
多くの「ことわざ・故事成語・四字熟語」を学ぶ過程で、どんな言葉が印象に残り、どんな言葉を好むかは人それぞれでしょう。
しかし、何かしらの「座右の銘」を選び取り、自分の信念の1つにしたり、判断や行動の基準にするのは良いことです。
こういうとき、「ことわざ・故事成語・四字熟語」はさまざまな側面を学習者に見せてくれます。
たとえば、
「一石二鳥」と「虻蜂取らず」
「三人寄れば文殊の知恵」と「船頭多くして船山に上る」
などは反対の意味を持っています。
このように、1つの事象について相反する価値観が存在することを学ぶことができます。
似た意味のことわざも、もちろんあります。
「塵も積もれば山となる」
「石の上にも三年」
「雨垂れ石を穿つ」
など、これらの言葉は、いずれも
「地道な努力の継続がいずれ大きな成果をもたらすこと」
を示しています。
このように、1つの価値観について多様な表現があることを知り、さらに、その価値観に一定の普遍性を感じることができます。
こうしたさまざまな価値観のあり方を吸収することで、ある価値観を絶対視するのではなく、柔軟な判断や思考を促すことにもつながると考えられます。
日本語は「第二の自然」です。
豊かな自然に恵まれ、四季が巡るこの国で、長い年月をかけて醸成された死生観、価値観、感性の継承は、言葉なくして不可能です。
「ことわざ・故事成語・四字熟語」の学習が、「第二の自然」としての豊かな土壌になっていることは疑いがありません。
抽象と具体の往復運動
「ことわざ・故事成語・四字熟語」の多くは、比喩表現が用いられています。
比喩表現に慣れることで、抽象的な概念を具体化したり、具体的な事象を抽象化する力が養われます。
たとえば、「猫に小判」を抽象化すると「価値が分からない人には、何の役に立たない」になります。
「価値が分からない人には、何の役にも立たない」を比喩を用いて具体化すると、「猫に小判」や「豚に真珠」となります。
こうした抽象と具体の往復運動は、表現力だけでなく、論理的思考力の土台にもなります。
学習のハードルを下げる
「ことわざ・故事成語・四字熟語」の学習には、難度の高い言語表現や学校で習わない漢字が多く出現します。
こういうものに継続的に触れることで、学校教育の内容が容易に感じられるようになる効果があります。
また、「学校で習わない難しいこと」を学習することは、多くの生徒にとって自信がつく要因にもなっているようです。
教科書をぱっと開いた時に、
「なんだか字がいっぱいあるな」のような威圧感を感じるのか、
「なんか漢字も少ないし、字も大きくて簡単そうだな」となんだかいけそうな気がするのか、
瞬時に感じる印象は学習の成果に大きく影響するでしょう。
「天網恢恢疎にして漏らさず」
「燕雀安くんぞ鴻鵠の志を知らんや」
「過ちては改むるに憚ることなかれ」
「軽挙妄動」
「鶏口牛後」
「堅忍不抜」
のような文字列を毎回のように教室で音読している小学生が、
学校の国語の教科書を難しいと感じる様子は想像しにくいものがあります。
このように、「ことわざ・故事成語・四字熟語」の学習は、学校での学習の難易度を下げる効果も期待できます。
音読による「読み」の力の強化
「ことわざ・故事成語・四字熟語」の学習では、繰り返し音読が基本になっています。
生徒は、毎回先生の前に座って、ある範囲の「ことわざ・故事成語」や「四字熟語」を音読します。
こうすることで、文章の構造やリズムを体感的に理解でき、漢字についても場面に応じたさまざまな読み方を身につけることができます。
「山川草木」を「やまかわくさき」ではなく「さんせんそうもく」
「春夏秋冬」を「はるなつあきふゆ」ではなく「しゅんかしゅうとう」
のように読めるようになってほしいと思いませんか。
教室では、まず繰り返し音読することを重視しています。
やがて生徒達は、何も見ずに言えるようになります。つまり、暗誦することができるのです。
基本的に「覚えてきなさい」とは言いません。
例外はありますが、「覚えるようになるまで繰り返す」が教室での主たる指導です。
もうすぐ覚えられそうだと指導者が感じたら、「覚えてきなさい」と背中を押すこともあります。
教室で行っているのは、「第二の自然」としての日本語を「生徒達の腹に据える」ことです。
使い捨ての紙コップのように言葉を消費することではありません。
このように、まず「読み」の力を鍛えることを出発点として、大量の言葉と表現を生徒達は自分のものにしてゆきます。
こうした学習を通して、語彙力が増大し、読解力の基礎が充実し、国語力全体の向上につながってゆきます。
そして、こうした学習の副次的な恩恵も無視することはできません。
それは、「記憶力の向上」という効果も得られることです。
記憶力は、高齢者でさえ、訓練すれば向上することが、近年の脳科学の知見で判明しています。
まして、まだまだ成長途上にある児童にとって、その効果は大きく作用するでしょう。
まとめ
教室で「ことわざ・故事成語・四字熟語」の学習を多く取り入れている理由について述べてきました。
見てきたように、「ことわざ・故事成語・四字熟語」の学習を継続することで、さまざまな効果を期待することができます。
幼児小学生は、しっかりとした基礎を形成するのに最も良い時期です。
自分の子の国語力について、心配している保護者の方が多くいらっしゃることは私も認識しております。
なればこそ、地道に実力を蓄えさせてあげたいと考え、日々の授業で生徒達と向き合っております。
今回も、最後までお読みいただきありがとうございます。