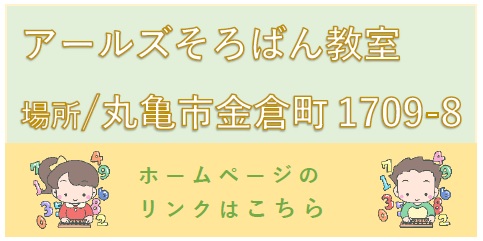そろばん学習と脳科学
「そろばんを習うと頭がよくなる」そういうことは、皆様にとっては耳タコでしょうが、これをきちんと説明することに挑戦してみました。
最後までお付き合いいただければ幸いです。
そろばん学習が、単なる計算力の向上だけではなく、
記憶力や集中力、さらには学習能力全般にまで影響するとしたら、どうでしょう。
実は、脳科学の最新研究から、そろばん学習が脳に与える影響が少しずつ明らかになってきています。
学習の鍵は「記憶力」
何かを学ぶとき、最も重要なのは「記憶力」です。
この記憶力を支えているのが、脳内のニューロンネットワークと、それを柔軟に変化させる神経可塑性です。
この神経可塑性を高めるには、2つの脳内物質が大きく関わっています。
①ドーパミン:達成感ややる気を生み出し、記憶の定着を促進
②アセチルコリン:注意力や覚醒度を高め、集中力を維持
これらの物質がうまく分泌されることで、脳は学習に最適な状態になります。
では、どうすればドーパミンとアセチルコリンがうまく分泌されるようになるでしょうか
n-back課題と記憶力の向上
ワシントン大学のシェリ・ミズモリ博士の研究によると、ドーパミンとアセチルコリンの分泌を促す「n-back課題」を継続的に行った学習者は、記憶力が向上しただけでなく、他の課題でも成績が向上したと報告されています。
つまり、「n-back課題」によって鍛えられるワーキングメモリ(作業記憶)は、脳全体の学習能力を底上げする可能性があるのです。
これについては、参考動画を記事下に貼っておきます。
そろばん学習と「n-back課題」の共通点
ここで注目したいのが、そろばん学習(特に暗算)です。
実はこの学習法、「n-back課題」と非常に似た認知プロセスを含んでいます。
・数字の保持と更新
・珠の動きを頭の中で操作
・不要な情報の抑制
・視空間イメージの活用
これらはすべて、ワーキングメモリをフル活用する高度な脳活動です。
つまり、そろばん学習者は、単なる計算力だけでなく、記憶力・集中力・注意力・処理速度など、さまざまな認知機能を鍛えているのです。
タイムボックス法との親和性
さらに、そろばん学習にはもう一つの魅力があります。
それは、タイムボックス法との自然な親和性です。
多くのそろばん教室では、「かけ算・わり算・見取算」の3種目を時間制限付きで練習します。
この「制限時間で区切る」学習法は、タイムボックス法そのものであり、以下のような効果が期待できます
・パーキンソン効果(時間が限られることで集中力が高まる)
・ドーパミンの活性化(達成感による報酬系の刺激)
・前頭前野の活性化(実行機能の強化)
・フロー状態の促進(没頭による高効率学習)
まとめ
YouTubeで脳科学の知見に基づく学習法や記憶のメカニズムに関する情報を漁っていたところ、「n-back課題」や「タイムボックス法」に突き当り、
「これはそろばん学習そのものではないか」
という感想を抱き、ざっくりですが今回の記事をまとめることにしました。
そろばん学習を通して、計算力だけでなく、記憶力をはじめとした脳全体の認知機能を高めることの根拠がお分かりいただけたと思います。
さらに、このタイムボックス法を用いたタスク管理は、高学年や有段者に取り入れてもらっています。
そろばんの良さに加えて、勉強法も将来の役に立つ訓練を教室で積んでもらえたらと願っています。
今回も最後までお読みいただきありがとうございます。
今回参考にした動画はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=wwZeEegSOsk&t=1681s