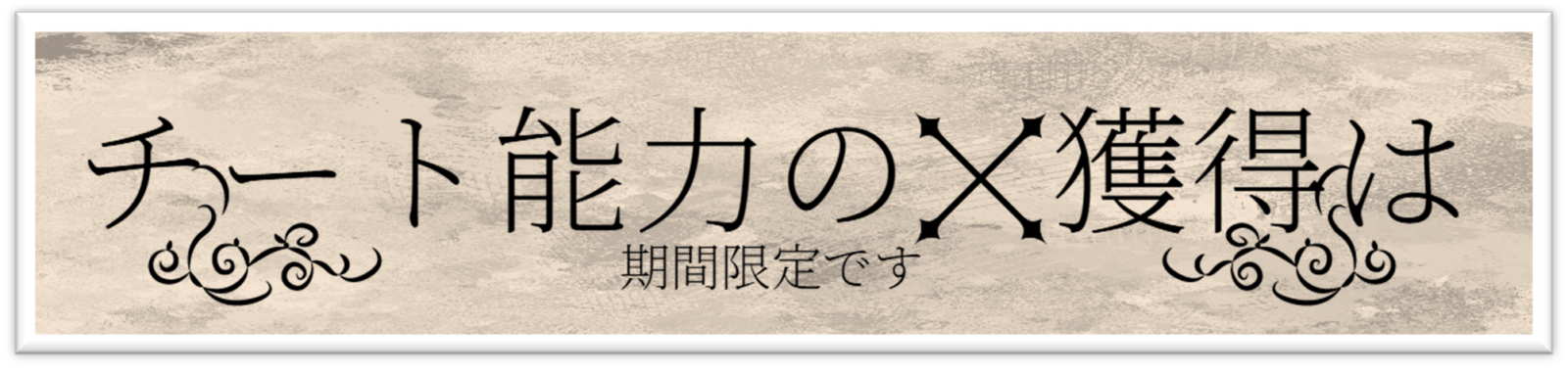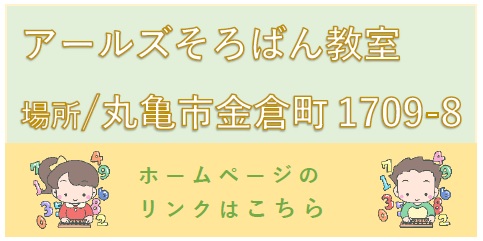算数と計算の関係
夜空を見上げながら、深いため息をついているのは20代前半の私です。
この頃は、まだ視力が良かったので、星の見える夜は天空にプレアデス星団を見つけては、その粒を数えるのが好きでした。
しかし、相変わらずため息は止まりません。
当時の悩みはこうです。
「あの生徒にいくら算数を教えても伸び悩むばかりだなあ……」
若い頃、丸亀のとある塾で講師をしていました(その塾はもうありません)。
担当教科は、小学生算数・小中学生国語・中学生英語です。
たまに、中3の理科や社会の授業もしていました。
何年も算数を教えているうちに、あることに気が付きます。
下の図をご覧ください。

算数を苦手とする生徒は、多くの場合C(計算苦手・算数苦手)のエリアにいます。
Cのエリアにいる生徒は、計算力を訓練することで、
エリアB(計算得意・算数苦手)からA(計算得意・算数得意)へ、あるいは、いきなりエリアAに移る可能性を高めることができます。
D(計算苦手・算数得意)にいる人たちは少数派なので、ここでは取り上げません。
差のつきかたの実例
A、B、Cにいる生徒について、実例を挙げましょう。
910mの道のりを14分で歩いたときの分速を求めましょう。
式は 910÷14 となりますが、
算数のよくできる生徒と苦手な生徒では、
たとえ同じようにこの式が書けたとしても、すでに式を書いた時点で大きな差があります。
算数の苦手な生徒によくみられるパターンは、
ここから
ア 無理矢理暗算で答えを出そうとして何十秒も考え込む。
イ 小さく走り書きで筆算のわり算をするのだが、計算間違いをよくする。
ウ 筆算の計算間違いに自分で気づくも、何度も書き直して時間がかかる。
などの症状が見られます。
それに対して、算数のよくできる生徒はこうです。
エ 即座にわり算の筆算を正確に行い、正しく答えを出す。筆算は走り書きではなく、しっかり書かれている場合が多い。
こんな塩梅なのですが、ここからさらによくできる生徒というのがいまして、
オ 式を書いた時点で、すでに頭の中に答えが見えている。
となります。
910÷14の式を書きながら、自動的に頭の中に答えの65が浮かんでいる状態です。
「すごいなあ」
と思う方もいらっしゃることでしょう。
しかし、暗算1級以上の実力があれば、普通のことです。
速さの〔分速〕を求める問題一題を例にとっても、このような調子ですから、
プリント1枚分ともなると、プリントにかかる時間も含めて大きな差になってしまうのは当然のことです。
高い計算力を身につけることは、算数という教科において圧倒的な差が生まれてしまいます。
かけっこならどうなるか
かけっこでたとえましょう。
AくんとBくんがスタートラインに立っています。ゴールは50m先です。
「よーい、ドン!」
2人が走りだしたと思った直後、なんとすでにAくんは涼しい顔でゴールラインに立っているではありませんか。まるで魔法のようです。
Bくんは、途中でつまずきながらも、10秒あまりをかけてやっとゴールを割ります。一生勝てる気がしません。
これと似た現象が算数で起こるとしたら、なかなか残酷だと思うのです。
私は、比較的若い時、いや、学生時代に塾講師のアルバイトを始めたときから、実はこのことに気が付いていました。
「算数が苦手なんだったら、そろばんを習って、さっさと計算力を身につければいいのに」
と思っていました。
実家がそろばん教室であるし、私もそろばんを祖父に習いました。
おかげで、算数のテストはいつもいい点数でした。
私の頭が良いわけでも、勤勉なわけでもありません。
ただただ、そろばんを習っていたおかげで計算が速かった。
たったそれだけの理由で、算数で苦労知らずだったのです。
小学校のうちに、そろばんを習って、ひとたび1級なり段位なりの実力を身につけてしまえば、算数数学で困ることなどほぼないばかりか、
周囲と圧倒的な差をつけながら、楽々とトップ集団の中に居続けられます。
これが、できるだけ多くの幼児・小学生にそろばんを習ってほしいと思う理由です。
チート能力の獲得は期間限定
「そろばんの剣」「国語の魔導書」というチート能力を手に入れることができるのは、幼児から小学校の時代に限られているため、小学校の間にぜひ手に入れてほしいと思います。
しかも、手に入れることで、子供はやらなくてよい努力から解放され、自由で伸び伸びとした小学生時代を送ることができます。
そもそも、今の小学生は、勉強時間が長すぎます。
わざわざ非効率的な学習のスパイラルに陥り、そこから不幸や劣等感、自由時間の少なさという状態を作り出しているように感じます。
戦士Aくんと戦士Bくん
たとえ話をしましょう。
ここで言うモンスターは、勉強する課題やテストだと思ってください。
これからモンスター狩りにダンジョンへ向かうところです。
ここで2人の戦士が登場します。
戦士Aは、普通の剣を持った装備です。
そして戦士Bは、右手にそろばんの剣を、左手に国語の魔導書を持っています。
2人ともよく戦い、同レベル・同数のモンスターを倒し、無事ダンジョンを攻略して帰ってきました。
ところが、戦士Aの持っていた剣はすでにボロボロで使い物になりません。体力はぎりぎりで、回復が必要ですが、次のダンジョン攻略に向け、また武器屋に走らなくてはなりません。
一方で、戦士Bの剣は、刃こぼれ一つありません。表情は涼しい顔をしており、まだまだ体力にも余裕がありそうです。
しかし、戦士Aには次の準備があるらしいので、待ってあげることにしました。その間、好きなことをして自由に過ごすことができます。
さて、どうやら戦士Aが武器屋からもどってきたようです。
新しい剣を手に、次のダンジョンへ向かうことにしましたが、戦士Aにはどうも余裕がなさそうです。
戦士A「次のダンジョンのモンスターだけど、倒し切れるか自信がないよ」
戦士B「え、そうなの?」
これまで相手にしてきたモンスターたちは、戦士Bにとっては楽々と倒せる相手でした。だから、次のダンジョンもたぶん楽に終わらせることができるだろうと思っていました。
しかし、戦士Aはちがうようです。そういえば、いつもいつも、ギリギリの戦いをして、戦いのたびに武器がボロボロになってしまいます。
しかも、モンスターの種類や、ダンジョンによって、準備する武器を毎回変えているようです。おかげで、戦士Aはダンジョンの分析やモンスター対策に追われて自由な時間がほとんどありません。
戦士Bにはわけが分かりません。
「そんなに準備しなくても、倒せるのになあ。それに、剣しか使わないなんて、不便そうだな。自分が楽にモンスターを倒せて、武器屋通いもしょっちゅうしなくていいのは、そろばんの剣と国語の魔導書のおかげなのかな?」
などとのんきに思っています。
戦士Bは、剣と魔法の両方を使えるのがチート級の能力であることを知りません。
勉強だとどうなるか
さて、これを勉強に置きかえましょう。
一般的な補習学習、つまり教科書準拠のワーク類を勉強したり、テスト対策を行ってくれる塾に通ったりしているのが、Aくんです。
悪くはありません。
しかし、Aくんは、テストのたびに消耗してしまいます。
単元ごとに、対策と練習を積まないとすぐに点数が悪くなってしまう。
そういうもろさがあります。
「読み書きそろばん」をやっているBくんは、攻撃力も防御力も高い武器を身につけているので、ほとんど対策しなくても、同じテストを楽々こなしてしまいます。
Aくんと、Bくんで、同じ95点を取ったとしても、その中身が違うことになります。
仮に、何かのテストでAくんが98点、Bくんが92点だったとして、それが何だというのでしょうか。
学校や塾で行われる単元テストの点数が、人生の分かれ目になるわけでもありません。
長期的に見れば、テストのたびに、長い時間を費やして点数を取りにいっているAくんよりも、ほとんど対策無しでいい点数が取れてしまうBくんでは、Bくんの方に将来性があることは明白です。
これは、決してBくんが努力していないということではありません。
Bくんの努力は「読み書きそろばん」に向けられているのです。
「読み書きそろばん」で培った、充実した基礎があるおかげで、学習のあらゆる場面で高いパフォーマンスを発揮することができます。
Aくんの努力の方向性については、
「それでもいいのですか?」
と思わざるを得ません。
獲得は期間限定
しかも、そろばんの剣・国語の魔導書は、手に入る時期が限られています。
中学生高校生になってからは、ほぼ不可能に近いと考えてください。
年長や小学校低学年あたりから始めるのが理想で、小学生でいる間がそれを手に入れるラストチャンスです。
学校の勉強を否定しているのではありません。
適切な時期に「読み書きそろばん」を訓練することで、大きな余裕を手に入られることを知っていただきたいのです。
第2回は思いのほか長くなってしまいました。
次回はそろばんがもたらす「熟達」の効用についてお話いたします。