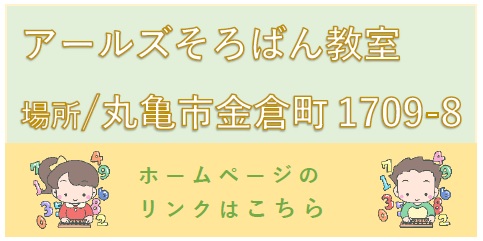結論から申し上げますと、「随時制」を採用している理由は、
ズバリ!
生徒と保護者の「自由」と「主体性」を最大限に尊重する
という経営方針に基づいています。
いったん話はそれるようですが、参考までにAIに、習い事の月謝について2点ほど質問してみました。
AIに『全国のそろばん教室の月謝の相場』を求めると以下のような解答になります。
全国のそろばん教室の月謝の相場は週に2~3回、1回1時間で4,000円~10,000円程度です。
地域や教室によって価格が異なるため、一概に言えませんが、4,000円~12,000円程度が相場とされています。
ここに出された回答を元に、月の授業料を平均すると
約7,000円です。
さらに、1時間当たりの単価を求めてみましょう。
1回の勉強時間を1時間、月に10回程度通った場合、
1時間当たりの授業料は700円周辺になります。
では、そろばんも含めたすべての習い事を含めた金額は、どうでしょうか。
再び、AIに『子どもの習い事の全国平均の1時間単価』を求めると以下のような解答になります。
子どもの習い事の全国平均の1時間単価は、教室や習い事の種類によって大きく異なりますが、おおよそ5,000円から10,000円程度が相場です。
ただし、これはあくまでも目安であり、教室や先生の知名度、レベルによって料金は変動します。
これで分かるように、そもそもそろばん教室というものは、
他の習い事に比べてべらぼうに安価な学びの場であり、
最強にコスパのいい習い事であることがご理解いただけたと思います。
ここでもう一度、アールズ国語そろばん教室の「随時制」の説明にもどします。
「随時制」とは極端な話、通う時間が「何分でもよい」ということです。
「何分でもよい」は「1分でもよいし5時間でもよい」
この幅の中で、自由に選べることで、
「自分で考えて決めなくてはならない。」
あるいは
「親と相談して決めなくてはならない。」
という状況が生まれます。
「決めるのは自分(たち)である」
という当事者意識を持ってもらいたいのです。
また、随時制であれば、
心の状態や体調によって柔軟に時間調整ができます。
さらに、
「あ、なんか時間があるから教室に行こう」という、
気まぐれな通い方も可能となります。
こうした自由度の確保は、一般的な塾や習い事の在り方とは真逆です。
一般的には、曜日や時間がかっちりと決まっていることが多いのですが、
決められた枠組みの中で行動することは、
規律に従って行動する訓練になる一方で、
「規律さえ守っていればよい」
という思考も呼び寄せます。
今の日本は、どこもかしこも規律だらけであるため、
世間全体を見渡したときに、
一定の自由度の中で自己決定するタイプの教室が、
少しは存在した方がバランスがよいと思っています。
また、時間の枠が決まることにより、否応なく発生するのが成果主義的思考です。
時間割がかっちりしているということは、
カリキュラムも固定的であり、
ある枠の授業に参加した生徒は、
そこで得られる成果を持って帰る(塾側から見れば持って帰ってもらう)という発想は避けられません。
これは一種の「~すべき論」です。
私たちは、ある種の「~すべき論」に囚われると、
思考が硬直化し、短期的な物の見方、
すなわち、
「教室に行ったのなら、そのかかったコストに見合う成果を持って帰るべき」
のような思考に陥りやすくなります。
しかし、人生はそう単純なものではありません。
たとえプリント1枚すら勉強しなかったとしても、
「先生とたわいない話をしただけ」
「教室の雰囲気を味わっただけ」
「勉強しようと思ったけど、やる気が出なかったので本を読んだだけ」
という日があってもいいと思います。
「あの日の『あれ』があったから、今日の自分がある」
というのは誰もが経験することです。
もしかしたら、その『あれ』の中に、
「先生とたわいない話をしただけ」
ということが入るやもしれません。
教室として成果がまったくないのは問題ですが、
毎度毎度、「教室での成果」に囚われることは、
随時制を採用する教室としては、ある種の息苦しさを感じます。
たしかに、ひとたび教室に入れば、
「ちゃんと勉強しなさい」
という圧はあります。
実際、私は
「勉強する気がないなら、帰れ」
「たたき出すぞ」
のような気を吐くことはまあまあ、あります。
ですから、ほとんどの生徒は一定の自覚を持って教室に入って来ます。
しかしながら、同じ
「勉強する気がないなら、帰れ」
という言葉を
上で述べたような、人間の弱さや不安定さに理解と自覚のある指導者が言うのか、
それとも、「べき論」に凝り固まった指導者が言うのかでは、全く響きが異なってくるものです。
また、
ある生徒に対しては
「勉強しないなら、帰れ」
という一方で、
ある生徒に対しては、
「やる気出ないなら、本でも読んでたら?」
とも言います。
えこひいきをしているわけではありません。
それぞれの生徒が、その時抱えている課題がそれぞれに違うため、
言葉かけもそれに応じて変えています。
他の生徒の邪魔をせず勉強することが課題となっている生徒もいれば、
次の目標に立ち向かう気力を奮い立たせることが課題となっている生徒もいます。
また、自分の家庭で「安心基地」を得られずに、心が安定しない生徒もいます。
これらの生徒達に対して、同じ声かけをする教師を
「一貫性を保ったよい教師」と見るのか、
「個性を見極めて柔軟に対応できる有能な教師」と見るのかは、
それぞれの価値観であるでしょう。
私はどちらかというと、後者ですが、
どちらも感じさせるのが、超一流の指導者であり、私の目指すところでもあります。
そして、主体性や自由についての一貫性を言うのであれば、
教室がどのような形でそれらの土台となっているかが問われます。
教室に来た生徒は、基本的にその日に何をするのかを自分で決めます。
これは決して放任主義というわけではありません。
学習内容について、生徒からの相談に応じることや、教師側が決めてあげることもあります。
また、タイミングを見計らって、生徒にレベルアップや、新しい学習を促すこともあります。
生徒の主体性と、教師の働きかけが有機的に作用して、教室の学習は成り立っています。
その絶妙なバランスは、
自由度が高く、本人が主体的に教室に関わらざるを得ない
「随時制」という仕組みが土台となっているのです。
ここまで生徒の自由と主体性について述べてきましたが、
実際問題、保護者の方にとって間違いなく便利な制度であるとも考えています。
日常をやりくりするのは本当に大変です。
私も三人の親なのではそのことは毎日身に染みています。
時間が過密過ぎて、体調面が不安になることも多々あります。
そういうわけで、この5月から休憩時間を少々頂くわけにしたのですが、
なにごともバランスが大切だとあらためて痛感しています。
最後に私が最近勉強になった動画を、思考の参考動画として載せておきます。
お時間のあるかたは是非ご覧ください。
今回の記事は以上です。