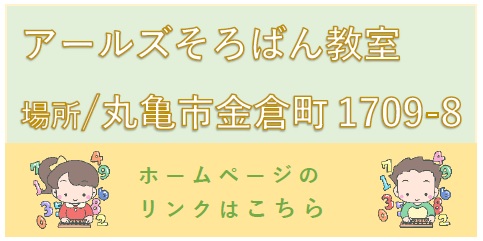『怪獣』は、アニメ『チ。地球の運動について』の主題歌です。
この歌詞を国語の先生が解説するとどうなるかをやってみましょう。
『怪獣』は、本人解説をはじめとし、いろいろな人が考察をすでに行っています。
したがって、特に皆さんが驚くような解釈や、目新しい視点はありません。
この記事では、『怪獣』の歌詞第1連だけを取り上げます。
何度でも
何度でも叫ぶ
この暗い夜の怪獣になっても
ここに残しておきたいんだよ
この秘密を
『チ。地球の運動について』は、15世紀のヨーロッパを舞台としています。
舞台となる「P王国」では、「C教」という宗教が広まっていたが、
地動説はその教義に反しており、
地動説を研究するだけでも、「異端」とされ、拷問や火あぶりに処せられます。
つまり「P王国」で地動説を研究することは、命がけだったのです。
こういうアニメの主題歌であるということを前提にすると、この歌詞の意味がより鮮明になります。
もう1つ前提情報を整理しておきます。
下の年表をご覧ください。
1468年 アルベルト・ブルゼフスキ(コペルニクスの師匠)が23歳でクラクフ大学に入学。
1491年 コペルニクスがクラクフ大学に入学。
1543年 コペルニクスが『天球の回転について』を出版。
1616年 地動説を支持したガリレオに対する第1回宗教裁判が行われる。
ガリレオは有罪。『天球の回転について』ローマ教皇庁により禁書目録の指定を受ける。
1633年 地動説の解説書『天文対話』を発行したガリレオに対し、第2回宗教裁判が行われ有罪となる。
1687年 ニュートンが『自然哲学の数学的諸原理』を発行。(万有引力の法則)
この年表の最初に登場するアルベルト・ブルゼフスキという人物は、
天動説に懐疑的であるものの、
地動説を積極的に支持するところまではいっていません。
しかし、月が楕円軌道を描いていることを発見したり、
月が常に同じ面を地球に向けていることを指摘したり、
その天文学的な業績は立派です。
この先生の存在が、コペルニクスに大きな影響を与えたことは容易に想像がつきます。
しかし、1543年にコペルニクスが『天球の回転について』を出版した後、
地動説に決定的な根拠を与える「万有引力の法則」が発見されるまで100年以上の歳月がかかっています。
物語の舞台は、コペルニクスが『天球の回転について』を出版する、さらに約100年前となっています。
さあ、やっと歌詞解説に入っていきましょう。
まず1~3行目
何度でも
何度でも叫ぶ
この暗い夜の怪獣になっても
倒置法が用いられています。
省略されているであろう主語を補って、並べかえてみましょう。
(ぼくは)この暗い夜の怪獣になっても、何度でも何度でも叫ぶ。
詩(歌詞)というものは、余計なものをそぎ落とした結果残った言葉です。
ならば、読み手は「たとえ ひらがな一文字で も」見落としてはいけません。
ここでは「怪獣に なって も」の「も」に注意を払います。
単に「なった」「なって」ではなく、「も」がくっついているということは、
ぼくは たとえ 暗い夜の 怪獣に なった としても、何度でも 何度でも 叫ぶ
のように言葉を補って考えることができます。
では、次に比喩表現についてですが、ここでの「怪獣」は
「だれを」「何に」たとえているのか。
この詩の前提となっている物語を考えると
「怪獣」=「異端者」
となります。
さらに、「怪獣」という言葉から想起されることを列挙してみましょう。
その1 「怪獣」は、怖い。恐ろしい。
その2 「怪獣」は、破壊的である。
その3 「怪獣」は、言葉が通じない。
その1から、その3まで想起されたものを、作品世界に引き寄せてみましょう。
怪獣=人々から恐れられ、これまでの常識を破壊する異端者であると同時に、一般人からすると理解に苦しむ存在。
ここでの、「怪獣」がどういうものをたとえているのか、だいぶ鮮明になってきました。
もう1つの比喩表現は「暗い夜」です。
先ほどの年表を見て分かる通り、
地動説がもはや疑いのないものになるまでには、長い年月がかかります。
「暗い夜」の反対は「明るい昼」です。
「明るい昼」を「地動説が世間に発表され、受け入れられた世の中」であるとするなら、
「暗い夜」は「地動説がまだ一部の人だけの秘密で、受け入れられていない世の中」のように捉えることができます。
まして単に「夜」ではなく「暗い夜」としているのは、夜明けが遠い先であることを感じさせます。
何度でも
何度でも叫ぶ
この暗い夜の怪獣になっても
この3行には
この世の中の常識をくつがえす地動説を信じる自分は、たとえ人々から恐れられ、理解されない存在になったとしても、何度でも何度でも叫ぶ。
という解釈が考えられます。
4~5行目
ここに残しておきたいんだよ
この秘密を
これも同じく倒置法です。
(ぼくは)この秘密をここに残しておきたいんだよ。
「この秘密」を、地動説についての知識であるとしたら、それを
「ここに残しておきたい」
とあります。
1~3行目と4~5行目の解釈を合わせてみましょう。
この世の中の常識をくつがえす地動説を信じる自分は、
たとえ人々から恐れられ、理解されない存在になったとしても、
何度でも何度でも叫ぶ。
自分は地動説の知識をここに残しておきたいんだよ。
こうしてみると「叫ぶ」がしっくりきません。
「叫ぶ」とは、どんな行動をたとえているのか。
この1~5行目だけに限定して解釈するならば、
さしあたりの結論は「残しておきたい」と考えられます。
残しておきたいのは、地動説の知識ですが、
では「誰に」「何に」と考えると、「地動説の知識を受け継ぐ者に」となるでしょう。
では、「叫ぶ」という行為は、単に目の前の何かに対して
「ガオーッ」
と文字通り叫ぶのではなく、
「この知識を受け継いでくれる未来の知らない誰か」
に対して「託す」という行為の比喩ではないかと私は感じます。
それは、時空を超越した異端者の想いです。
この知識よ、どうか誰かに届くことを祈る
という雰囲気ですね。
かっこいいですね。
ということで、
サカナクション『怪獣』冒頭部を国語の先生が解説してみた
でした。
異端者の皆さん、お楽しみいただけましたでしょうか。
せっかくなので、この曲のMV(バンドオリジナルとアニメコラボ)を貼っておきます。