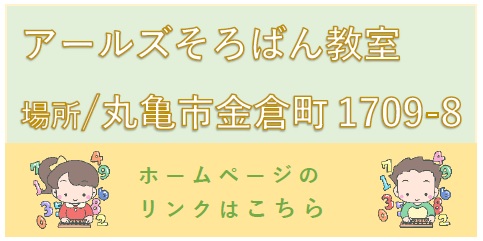さて、前回記事で解説した「日本人の内的自己の危機」に対して、
これを社会的な病理であると考えたとき、
私たちはこの問題にどのように向き合っていけばよいか。
「教育にできること」という視点から考えました。
まず、今の教育制度のレールに乗って、普通に小中高大と進んでいけば、
前述したような、空虚な内的自己を持ったままの一人の社会人が出来上がりがちなのは、世相を鑑みれば自明のことに思われます。
現在の教育による優劣の価値観は、
「偏差値(テストの点数、または学年順位)」「学歴」による評価が支配的です。
もっと言えば、それによって人間的価値の優劣を、意識の奥底で決めてしまっている自分達がいるのではないでしょうか。
これは、毎日授業をしている私の肌感覚でも感じられるところですが、小学校1年生にして、すでに
「テストの点数が高い=いい子・頭が良い子」
という価値観を疑いなく受け入れている生徒がほとんどです。
私からすれば、ほとんど病人を相手にしているような気分になってしまいます。
これを「健全である」と無批判に受容するような親は論外として、
「まあ、仕方がない」
「それが世の中だ」
という諦念と
「自分の子が変な点数を取ると心配になる」
という、依り代を失った不安感、
そして、
「やはり、安定して食っていくためならなるべくいい成績を取って、いい学校に」
という妥協と安全欲の混合物。
この複数の糸が織りなす絨毯の上に子供達を乗せ、
「なるべく大過なく」「なるべく安全に」
社会人として食っていけるように運ぼうとする。
これが、私から見た「親」に関する典型的な姿勢です。
ここで注意したいのは、
私の中に、「親批判」「保護者批判」をする意図は寸毫もないことです。
なぜなら、
「その親もまた、元子供であり、日本人として大人のたすきを受け取り、次につないでいる一人である」
という構造を見ているからです。
この章のはじめに「社会的な病理」という言葉を使った通り、この問題は
「親が悪い」
「学校が悪い」
のような犯人捜しをして解決する問題ではありません。
この病理は、戦前から続いている連鎖だからです。
複雑に絡み合う問題の通低音を鳴らすのは、日本社会が抱える矛盾であり、
その矛盾から発生する、多種多様な「おかしな価値観」が私たちを苦しめています。
その、「おかしな価値観」の一つが、
高偏差値を賞賛し、
学歴が高いほど「安全で安定」「勝ち組」「優秀」であるという考え方です。
この価値観はあらゆる意味で「おかしい」です。
ちょっと考えれば分かることですが、人間の営みはそんなに単純なものではありません。
ちょうどこの記事の源泉となっている浜崎氏も、素晴らしい文芸批評家ですが「高偏差値」「高学歴」であるとは決して言えません。
そのような例は枚挙に暇がないので話を戻します。
こうした価値観のおかしさを指摘する教育関係者がたくさんいるにも関わらず、状況が好転しないのはなぜでしょうか。
多くの子育て中の親が、一定の違和感を抱いていることもまた、一面の真実としてあるものの、
そうした「高偏差値」「高学歴」価値観を、「状況として甘受する」ことを多くの親が選択しているのが実情です。
この「高偏差値」「高学歴」を重視する価値観は、
「東京大学を頂点とする」ピラミッド型の価値体系だと私は感じているのですが、
このピラミッドから外れても尚、「勉強をする意味」を定義し、伝え、実践できる教育者が少ないことが大問題なのです。
それは代替案と言ってもいいし、逃げ場という人もいるかもしれないのですが、
この際、そこに対する呼び方などは私にとってはどうでもよく、
「勉強をする意味」の答えが、
「東京大学を頂点とする」ピラミッド型の価値体系でしか説明できなくなっていることが問題です。(以下、この価値観を『東大教』と呼ぶことにします)
別の言い方をすれば、多くの子育て中の親にとって、
『東大教』に代わる、説得力を持った「学びの代替案」が用意されていない現状があることは否定できません。
まして、このような一元主義的で一神教的なものが、
二千年以上にわたり「八百万の神々」を信仰してきた日本人の身の丈に合うはずがないと思ってしまいます。
私のことをよくご存知の方は、この後何が言いたいのかは大体想像がつくと思うのですが、
「寺子屋形式の読み書きそろばん」は、「勉強をする意味」の代替案として成立すると確信しています。
代替案どころではなく、むしろ解決策として大きく機能するでしょう。
ただし、「読み書きそろばん」によって、完璧で理想的な日本人を育てようとする意図は全くありません。
自然に中今を生きる人になってもらえればよいと思っています。
私の中では、
中今を生きる人=内的自己がしっかりしている人
と理解しています。
そういう文脈の中で、「読み書きそろばん」は、子供達の内的自己を育てる大きなエネルギーとなり得ると考えています。
「読み書きそろばん」が、どのような形で子供達の内的自己を育てるエネルギーになるのかは、また別の機会にお話することにします。
最後に、この記事を書く根本を支えた、浜崎先生の参考動画を二本ご紹介いたします。明治以降の日本人の精神の病み具合が、とても分かりやすく語られています。