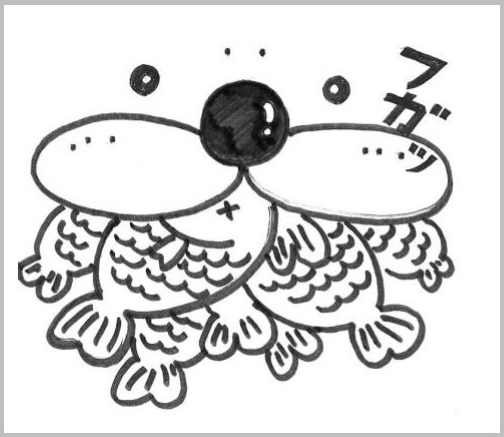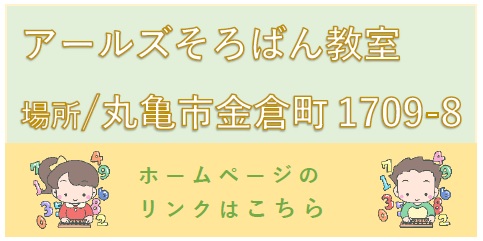素読に対してよくある批判として
「意味は教えなくて大丈夫なのですか?」
というものがあります。
実際に、保護者に面と向かって言われたことがあります。
「意味理解」を後回しにする指導、
すなわち素読指導を受けたことがない人が多すぎて、
その良さを理解できる人が絶滅しかけているのが、
今の日本の現状です。
また、「意味の分からない文章を読む」という行為は、
小さな子供達にとっては平気なのですが、
成長するにつれて、
「意味不明な文章を声に出して読むなんて苦痛でしかない」
「こんなことやって意味あるのか?」
などのように、違和感や抵抗感を示す場合が増えてきます。
そもそも「意味が分かる」とはどういうことなのか。
それこそ、先の記事で引用した今井むつみ先生が解説しているスキーマ理論を勉強すれば、素読における意味理解の後回しは妥当な学習方法であることが分かります。
私もパターンに分けながら、例をいくつか挙げましょう。
例1 解像度によって意味が変化する場合
祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。
沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。
皆さんよくご存じの、平家物語冒頭部です。
それでは、これを「現代語訳」してみましょう。
祇園精舎の鐘の声には、諸行無常の響きがあります。
沙羅双樹の花の色は、盛者必衰の理を表しています。
さて、皆様。よく意味が分かりましたでしょうか。
これで
「そうか、そういう意味だったのか!」
と言う人がいたら、ちょっとおかしいですね。
現代語訳を見ただけでは、分からないことだらけというのが普通の感覚だと思います。
仮に、この2行の本当の意味を説明するために授業を行うとしたら、
60分の講義でも時間が足りないと感じます。
まずもって、「祇園精舎」とは何なのか。
「諸行無常」という言葉はどこから来ているのか。
これを解説するだけでも、深掘りすれば1時間を軽く超えます。
このように、「意味理解」には、その意味をどれくらい深く理解しているかという「解像度」の問題がついてまわります。
例2 解釈が何通りもある場合
また、「意味」というのは、同じ言葉でも人によって解釈が変わることはごく自然なことです。
仏教用語に「色即是空」という言葉があります。
非常に深い言葉であり、十人の和尚様がいれば十通りの説教を拝聴することができるでしょう。
仏教用語ではない、みんながよく知っている言葉でも同様のことは起こります。
国歌「君が代」についてですが、
この「君」を「天皇」であると解釈する人、またそのように教わった人は多いのではないでしょうか。
これは、明治政府が勝手に決めた意味で、もともとは「親しいあなた・大切なあなた様」ぐらいの意味でした。
この歌の原形は、古今和歌集・賀の歌の冒頭に、読み人知らずとして収録されています。
わが君は 千代に八千代に さざれ石の 巌となりて 苔のむすまで
ようするに、祝いの席で、宴席の主人の長寿を祈る歌です。
そのような、平和で素朴な歌を、国家統合の道具にしてしまったせいで、後顧に憂いを残す残念な結果となってしまいました。
幕末の志士や、維新の元勲を持ち上げる風潮がずっと続いておりますが、明治維新は、これを再批評する時期に来ていると私は感じています。
例3 個人の経験や背景知識によって意味が変わる
さて、話を戻しましょう。
同じ人間が、同じ本を読んでも、それを読んだ時と場所が変われば、ちがう意味を汲めるというのは、誰もが持っている経験でしょう。
また、その人が信じるものの違いによって、同じ物語でも全く違う世界観で捉えられる場合があります。
たとえば、宇宙人の存在を信じる人にとっては、
「かぐや姫」は宇宙人の赤ちゃんを大切に育てた話だし、
「浦島太郎」はアブダクション(宇宙人にさらわれること)の物語として読み手に迫ってくるでしょう。
意味は後回しでよい
このように、ひと口に「意味」と言っても、これをどう扱うかは、大変難しい問題です。
また、人生経験や背景知識、分析的思考力がまだまだ未熟な子供達に、小難しい意味を講義するのは、大変非効率です。
だからこそ、素読という手法を用いて
「意味理解を後回しにして、とりあえずたくさんの言葉を学ぶ」
これを私たちのご先祖様たちは行ってきたのだと思います。
もちろん、辞書を引きつつ、引用元を参照しつつ精読するのもとても大切な勉強方法ですが、
ここでは素読について論じておりますので、精読の素晴らしさについてはここでは言及しません。
アールズの生徒は、幼児と小学生がほとんどです。
「覚えないでね」
とお願いしても、勝手に頭が記憶してしまうような年齢です。
その年齢的なことを考えたとき、意味を確認しながら、ゆっくり読み進める指導は、もっさりしていてとてもちぐはぐな感じがします。
素読は、意味理解は後回することで、大量の詩文をインプットすることが可能になります。
この大量のインプットが元になって、後の高度な意味理解の土台となります。
目の前にあるテキストについて、何が何でも意味が分からなくては先へ進めないというのは、大きな機会損失です。
計算(算数)でも意味は後回し
最後になりますが、素読における「意味後回し」は痛烈に批判されることが多い一方で、
計算における「意味後回し」はことごとく素通りされる現象があります。
そろばん学習について、教室では早ければ年長児に「かけ算」「わり算」を教えます。
このとき、「かけ算の意味」「わり算の意味」を教えることはせず、ひたすらそろばん上での「やり方」を繰り返します。
これでちゃんと算数が得意な子供になってくれるのですから、何ら問題はありません。
国語も算数も、ややこしい意味は、後回しでも大丈夫ということなのです。
ただし、教室で意味の解説を全く行わないわけではありません。
充分素読をして、その詩文を自分のものとした生徒に対しては、
「これはこのような意味である・・・・・・」
と折々に解説していることは付記しておきます。
また、ここだけの話ですが、
幼児小学生で素読をしていない生徒にとって、
中学高校で教科書に出てくる古典作品たちは、
ほぼ初見で出会うことになってしまいます。
そんな子供達と、
「あ、これ知ってる。見たことある」というアールズの子供達とでは、
理解度が全く違うことも付け加えておきます。
さて、記事の最後に、素読や暗誦について触れられている動画を1つ紹介したします。お時間のあるときにゆっくりご覧ください。