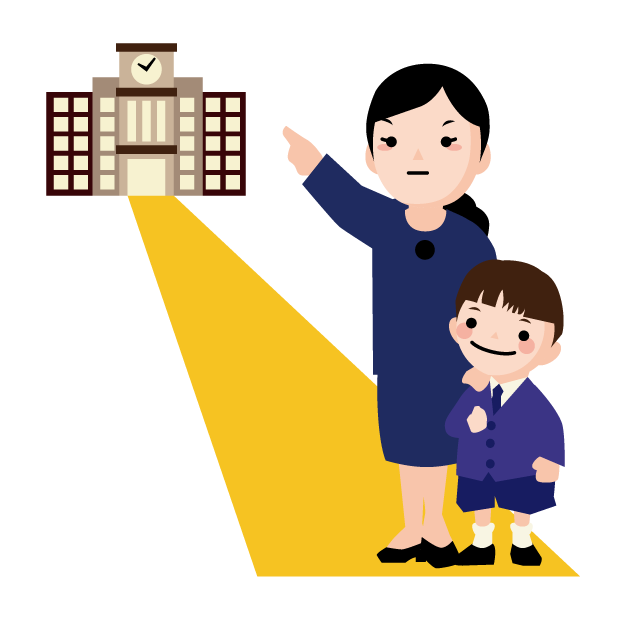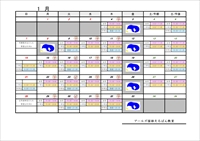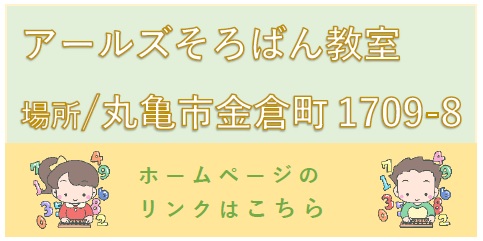浜崎氏は、「和魂洋才」という、明治維新におけるスローガンが、日本人の内的自己が失われる大きな契機になったという意味のことを述べています。
「和の精神を保ちつつ、西洋の技術を受け入れていこう」
というのが「和魂洋才」です。
壮大でありながら、ともすれば民族的危機を招きかねない実験です。
当時の世界情勢を鑑みれば、やむを得ない側面があったことはいえ、
「そんなこと本当に可能なのか?」
という路線に日本全体が突っ込んでいきました。
「和魂洋才」「脱亜入欧」「富国強兵」
これらは、個人から見れば分かりやすい外的抑圧です。
これに苦しんだのが、当時の知識人であり、文学者です。
夏目漱石は、内的自己(和)と外的自己(洋)との折り合いをつけるために苦悶しました。
芥川龍之介は、内的自己と外的自己の折り合いがつかず、「ぼんやりとした不安」を口にして自死に至りました。
多くの人が、日本人でありながら、その生活様式や振る舞いは「西洋的」にする必要がありました。
当時の大多数の日本人にとって「西洋的」な振る舞いは、まさに外的自己による行い、すなわち適応だったことは疑いありません。
たった数十年前まで、和服を身につけ、ちょんまげを結っていた彼らが、髪を伸ばし、ズボンをはき、ネクタイを締める。
現代の我々からは、想像しずらい「自己の内面にうごめく何か」があったに違いありません。
世間と接するときだけ、「西洋的」に振る舞い、家の中では伝統的な生活を保っている場合もあったでしょう。
しかし、外面(そとづら)だけでなく、ある場合は内的自己の安心基地であるべき家の中にも浸食してきました。
ここで私の頭に浮かんだのが、太宰治『斜陽』の冒頭です。
朝、食堂でスウプを一さじ、すっと吸ってお母さまが、「あ」と幽かな叫び声をおあげになった。
もう、ダメだなこりゃって思いますよね。
すでに朝食が、ご飯と味噌汁じゃないんですから。
現代の私たちの感覚からすれば、「え、ダメなの?」と思うかもしれませんが、
『斜陽』が出版されたのは昭和23年です。
参考までに、当時の農業従事者の割合は、日本の労働人口の4分の3を優に超えていました。
朝からスープって、おいおいおいおいって感じです。
『斜陽』は戦後の没落貴族を描いた破滅的物語ですが、
その登場人物たちは、もう始めから内的自己が和と洋のあいだを行ったり来たりしています。
そして、「スウプ」を「スプウンで」掬って飲んでいる「お母さま」はこの数ページ後で「海苔で包んだおむすび」を食べることも付け加えておきます。
「和」と「洋」を行き来する、ある没落貴族の家族の振る舞いや内面を
太宰が意識的に描写しているのは当然として、
あらためて『斜陽』を読み返したときに
「私は一体、何を見せられているんだ?」
という感想を思わず抱いてしまいます。
その冒頭部では、必然的に起こるであろう、
「和」と「洋」の板ばさみとなった自我の苦悩
が全くと言っていいほど描かれてはいません。
それどころか、「西洋」という価値観を受容した上で、
日本人としてそれが整理されていない、
地に足のついてない、空虚な自我――その空虚さへの無自覚なさまを見せられているのではないでしょうか。
そして、この登場人物たちの空虚な自我への無自覚を、私たち現代の日本人は笑うことができないのです。
つまり、明治より始まった西洋化の流れの中で私たちが失ったものは、
「西洋的なもの」と対峙し得る内的自己の強かさであり、
「敗戦」というものを経て、その内的自己の在り方について問い直す力さえ失ってしまったのです。
そこにあるのは、依り代を失った、空虚な、内的自己に無自覚なまま、いくらでも「世間」に迎合しようとする外的自己です。
日本という土地に生まれ、生物学的に日本人を親に持っているだけの、外的自己への抑圧に従順な東洋人たちが「日本人ですが何か・・・?」という顔をしてそこかしこに立っているのです。
あるいは、内的自己の声に耳を傾けられない、無視する。
あるいは、内的自己と外的自己の折り合いが付かずに、ひたすら抑圧を感じている、不条理を感じている。
先ほども触れたように、その不条理の正体は、明治維新を発端とし、
続く「敗戦」を通してさらに複雑な要素が絡み合うことになりました。
次回へ続きます